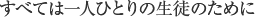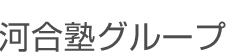スタッフからのお知らせK会本郷教室
28件の新着情報があります。 1-10件を表示
━【「言語学をのぞいてみよう その43」(元K会英語科講師:野中大輔) 】━
2026年1月13日 更新
━【「言語学をのぞいてみよう その43」(元K会英語科講師:野中大輔) 】━
★このコラムでは、言語学を研究している筆者(元K会英語科講師)が、英語・言語学・外国語学習・比較文化などの話題をお伝えしていきます。★
「あけましておめでとうございます」から始める言語観察
2026年になりました。お正月になって「あけましておめでとうございます」と言った(あるいは、言われた)という方が多いのではないかと思います。私もその1人ですが、そういえば、「ございます」を「ございました」にして「あけましておめでとうございました」なんて言うとしたら、かなり違和感があるなと思いました。「おめでとうございます」に対して「おめでとうございました」は普通あまり使わないことについては、以前から少し気になっていたのですが、お正月を迎えて、ふとそのことを思い出しました。
せっかくなので、「おめでとうございました」が実際にどの程度使われているか、「コーパス」と呼ばれるデータベースで調べることにしました。コーパスとは、実際に使用された話し言葉や書き言葉のデータを集めて、コンピューター上で検索可能にしたもののことです。今回は、日本語研究でよく使用される『現代日本語書き言葉均衡コーパス』で検索してみます。これは、その名の通り、書き言葉(小説、新聞、ブログ記事など)に特化したコーパスであり、1億語規模の日本語表現が収録されています。
現代日本語書き言葉均衡コーパスで「おめでとうございます」と「おめでとうございました」を検索すると、見つかった用例数は以下の通りでした(ひらがな表記で検索)。
(1)「おめでとうございます」628件/「おめでとうございました」18件
「おめでとうございました」の用例数は「おめでとうございます」の30分の1ほどであり、私たちが普段接する機会が多いのは圧倒的に「おめでとうございます」のほうだと言えます。なお、(1)の検索結果に含まれますが、「あけましておめでとうございます」だと62件、「あけましておめでとうございました」だと0件です。
他の挨拶表現として「おはよう」はどうでしょうか。「おはようございます」と「おはようございました」で検索すると、次のようになりました。
(2)「おはようございます」815件/「おはようございました」1件
「おめでとうございました」よりも極端な結果で、「おはようございました」の用例はわずか1件でした。では、こういった挨拶系の表現で、「ございました」がごく普通に用いられるものはないのでしょうか。ここで思いついたのが「ありがとうございました」です。これは「ございます/ございました」どちらも自然な表現ですね。先ほどと同じく、「ありがとうございます」と「ありがとうございました」で検索すると、次のような結果が出ました。
(3)「ありがとうございます」1,741件/「ありがとうございました」2,165件
「ありがとうございます」と「ありがとうございました」では、どちらも用例数が多く、そのうえで、おもしろいことに、「ございました」のほうが使用頻度が高いわけですね。今回は書き言葉のコーパスを使いましたが、話し言葉ではどうかなど、さらに興味が湧いてきました。
「ございます」が言えるなら「ございました」が言えてもよいはずなのに、「おめでとうございました」や「おはようございました」は普通言わない。では、挨拶系の表現なら「ございました」が一律で不自然になるかといえば、「ありがとうございました」はむしろよく使われる。このように、言語には、言えそうで言えない表現があったり、ある面では似ているように見えて別の面では異なる特徴を持った表現があったりするものです。もっと整然とした体系であってほしいと思う人も、こういった凸凹な側面があることを面白いと思う人もいて、私はたまたま後者で、だからこそ言語の観察を楽しんでいるのだろう――そんなことを考えるお正月でした。
[補足]
現代日本語書き言葉均衡コーパスにアクセスするやり方はいくつかありますが、今回は検索アプリケーションの1つである「中納言」を用いて、「文字列検索」と呼ばれる検索を行いました。「中納言」は利用登録が必要ですが、登録不要でだれでも利用できる簡易版の「少納言」もありますので、興味があればアクセスしてみてください。
https://shonagon.ninjal.ac.jp/
★このコラムでは、言語学を研究している筆者(元K会英語科講師)が、英語・言語学・外国語学習・比較文化などの話題をお伝えしていきます。★
「あけましておめでとうございます」から始める言語観察
2026年になりました。お正月になって「あけましておめでとうございます」と言った(あるいは、言われた)という方が多いのではないかと思います。私もその1人ですが、そういえば、「ございます」を「ございました」にして「あけましておめでとうございました」なんて言うとしたら、かなり違和感があるなと思いました。「おめでとうございます」に対して「おめでとうございました」は普通あまり使わないことについては、以前から少し気になっていたのですが、お正月を迎えて、ふとそのことを思い出しました。
せっかくなので、「おめでとうございました」が実際にどの程度使われているか、「コーパス」と呼ばれるデータベースで調べることにしました。コーパスとは、実際に使用された話し言葉や書き言葉のデータを集めて、コンピューター上で検索可能にしたもののことです。今回は、日本語研究でよく使用される『現代日本語書き言葉均衡コーパス』で検索してみます。これは、その名の通り、書き言葉(小説、新聞、ブログ記事など)に特化したコーパスであり、1億語規模の日本語表現が収録されています。
現代日本語書き言葉均衡コーパスで「おめでとうございます」と「おめでとうございました」を検索すると、見つかった用例数は以下の通りでした(ひらがな表記で検索)。
(1)「おめでとうございます」628件/「おめでとうございました」18件
「おめでとうございました」の用例数は「おめでとうございます」の30分の1ほどであり、私たちが普段接する機会が多いのは圧倒的に「おめでとうございます」のほうだと言えます。なお、(1)の検索結果に含まれますが、「あけましておめでとうございます」だと62件、「あけましておめでとうございました」だと0件です。
他の挨拶表現として「おはよう」はどうでしょうか。「おはようございます」と「おはようございました」で検索すると、次のようになりました。
(2)「おはようございます」815件/「おはようございました」1件
「おめでとうございました」よりも極端な結果で、「おはようございました」の用例はわずか1件でした。では、こういった挨拶系の表現で、「ございました」がごく普通に用いられるものはないのでしょうか。ここで思いついたのが「ありがとうございました」です。これは「ございます/ございました」どちらも自然な表現ですね。先ほどと同じく、「ありがとうございます」と「ありがとうございました」で検索すると、次のような結果が出ました。
(3)「ありがとうございます」1,741件/「ありがとうございました」2,165件
「ありがとうございます」と「ありがとうございました」では、どちらも用例数が多く、そのうえで、おもしろいことに、「ございました」のほうが使用頻度が高いわけですね。今回は書き言葉のコーパスを使いましたが、話し言葉ではどうかなど、さらに興味が湧いてきました。
「ございます」が言えるなら「ございました」が言えてもよいはずなのに、「おめでとうございました」や「おはようございました」は普通言わない。では、挨拶系の表現なら「ございました」が一律で不自然になるかといえば、「ありがとうございました」はむしろよく使われる。このように、言語には、言えそうで言えない表現があったり、ある面では似ているように見えて別の面では異なる特徴を持った表現があったりするものです。もっと整然とした体系であってほしいと思う人も、こういった凸凹な側面があることを面白いと思う人もいて、私はたまたま後者で、だからこそ言語の観察を楽しんでいるのだろう――そんなことを考えるお正月でした。
[補足]
現代日本語書き言葉均衡コーパスにアクセスするやり方はいくつかありますが、今回は検索アプリケーションの1つである「中納言」を用いて、「文字列検索」と呼ばれる検索を行いました。「中納言」は利用登録が必要ですが、登録不要でだれでも利用できる簡易版の「少納言」もありますので、興味があればアクセスしてみてください。
https://shonagon.ninjal.ac.jp/
━【「音楽から見る数学15」(元K会生・元K会数学科講師:布施音人) 】━
2025年12月15日 更新
━【「音楽から見る数学15」(元K会生・元K会数学科講師:布施音人) 】━
★このコラムでは、数学と音楽の両方に魅せられてきた筆者が、数学と音楽の共通点を考える中で見えてくる数学の魅力について、筆者なりの言葉でお伝えしていきます★
― ジャズのアドリブのしくみとコード進行 ―
こんにちは。元K会数学科講師の布施音人です。
突然ですが、みなさんはいわゆる「ジャズ」を聴いたことがありますか?また、ジャズに対してどんな印象を持っているでしょうか。
ジャズがどんな音楽なのか、その範囲を細かく定義することは難しいのですが、ジャズの大きな特徴として、曲の中に「アドリブソロ」という場が存在していることが挙げられます。今回はそのアドリブソロのしくみについてお話しようと思います。
歌の曲で、1番、2番、3番...というように歌詞がついているものを思い浮かべてみて下さい。小学校で歌った唱歌でもよいし、J-POPのヒット曲、アニメソング、なんでもよいです。すると、多くの場合、2番と3番の間や最後のサビの前に伴奏だけの部分が少し多めにあるのではないでしょうか?すごく雑に言うと、ジャズのアドリブソロはこの伴奏だけの部分を発展させたものです。
ジャズミュージシャンたちの共通のレパートリーである「スタンダード」と呼ばれる一連の曲があります。その多くは、20世紀前半のアメリカの映画やミュージカルの楽曲です。それらの楽曲は、多くがひと回し32小節で、歌詞が2番や3番までついています。そして、たとえば歌詞が3番まであるとすると、1番、2番と2周歌ったあと、一旦楽器だけで1周分演奏し、最後にまた歌が入って3番を歌う、という構成でよく演奏されていました。ジャズミュージシャンたちは、この楽器だけの部分を1周で終わらせずに何周も何周も繰り返し、そこでアドリブを繰り広げていったのです。
ジャズミュージシャンたちがスタンダードを演奏するときの一曲の構成は大まかに次のようになります。まず、曲に入る前の序奏として、4小節か8小節程度、曲の終わりの部分やお決まりのイントロを演奏します(ない場合もあります)。その後、「前(まえ)テーマ」と呼ばれる部分が始まります。ここでは、たいてい1周か2周、その曲のメロディを演奏します。そのあとが「ソロ」です。元になった曲を変奏する形で、それぞれの奏者が順番にアドリブソロを演奏します。たとえば、サックス、ピアノ、ベース、ドラムスの4人で演奏しているのであれば、始めにサックスがソロを吹き、もういいかなと思ったらピアノに受け渡し、ピアノソロも終わったら次にベースソロ、という順に進むことが多いです。この間もずっと、1周32小節の曲であればその32小節をグルグルと繰り返しているという形です。ドラムのソロにあたる部分は、ドラム以外とドラムとの掛け合いによる「バース」(bars、小節(bar)の複数形)と呼ばれるやり方をすることが多いですが、この間も1周32小節の形式は守られます。そして最後にようやくメロディを1周演奏して(「後(あと)テーマ」と呼ばれます)、短いエンディングを付けて一曲が終わります。
このように、ジャズのアドリブソロとは、あくまで元の曲の変奏を何周も何周もやっているものだと言えます。この変奏を行うときに指針となるのが、コード進行です。
学校の音楽の授業で、CM7(Cメジャーセブンス)やFm7(Fマイナーセブンス)などについて教わったでしょうか?コード(=和音)とは、異なる高さの音が同時になってできる音のことです。もちろんそのようなものは膨大な数考えられますが、各音の音名と一番低い音(ルート)とに着目して分類し名前を付けたものが、先述したCM7のような「コードネーム」です。メロディとコードネームだけが書かれた譜面を「リードシート」と呼びますが、ジャズミュージシャンたちはこのリードシートだけを見て、自分が演奏するべき役割(低音を支えるのか、メロディを吹くのか、中音域で和音を弾くのか、など)を考え、演奏していきます。
ところで、コード進行は思った以上に曖昧で、また自由な概念です。まず、同じ曲でも複数のコード進行が存在する場合があります。オーケストラの曲として書かれた原曲の段階で、アレンジャーの遊び心からバリエーションが生まれている場合もありますし、後世のミュージシャンがメロディに合う他のコード進行を持ってきて演奏し(リハーモナイゼーションと呼びます)、それが広まったものもあります。また、異なる曲どうしで共通するコード進行を見つけ、メロディやアレンジのアイデアを引用するということもよく行われます。これは、コードネームが記号であることの利点でしょう。
コードネームは、音楽の様々な要素(音色、音量、旋律の動きなど)を捨象して抽出された記号ですが、むしろそれを介して様々な音楽が生まれ花開いているとも言えます。そこにはパズル的な面白さや、一見異なるものに共通点を見出すという数学的思考がふんだんに隠れています。私の身の回りを見ても、数学とジャズの両方に魅力を感じる人は多いようです。みなさんも是非ジャズの世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。最後に、今回は紙面の都合もありコード進行という音の高さに関する話に終始しましたが、ジャズにはそれ以上に大切なリズムの要素もあることだけは書き添えておきます。
★このコラムでは、数学と音楽の両方に魅せられてきた筆者が、数学と音楽の共通点を考える中で見えてくる数学の魅力について、筆者なりの言葉でお伝えしていきます★
― ジャズのアドリブのしくみとコード進行 ―
こんにちは。元K会数学科講師の布施音人です。
突然ですが、みなさんはいわゆる「ジャズ」を聴いたことがありますか?また、ジャズに対してどんな印象を持っているでしょうか。
ジャズがどんな音楽なのか、その範囲を細かく定義することは難しいのですが、ジャズの大きな特徴として、曲の中に「アドリブソロ」という場が存在していることが挙げられます。今回はそのアドリブソロのしくみについてお話しようと思います。
歌の曲で、1番、2番、3番...というように歌詞がついているものを思い浮かべてみて下さい。小学校で歌った唱歌でもよいし、J-POPのヒット曲、アニメソング、なんでもよいです。すると、多くの場合、2番と3番の間や最後のサビの前に伴奏だけの部分が少し多めにあるのではないでしょうか?すごく雑に言うと、ジャズのアドリブソロはこの伴奏だけの部分を発展させたものです。
ジャズミュージシャンたちの共通のレパートリーである「スタンダード」と呼ばれる一連の曲があります。その多くは、20世紀前半のアメリカの映画やミュージカルの楽曲です。それらの楽曲は、多くがひと回し32小節で、歌詞が2番や3番までついています。そして、たとえば歌詞が3番まであるとすると、1番、2番と2周歌ったあと、一旦楽器だけで1周分演奏し、最後にまた歌が入って3番を歌う、という構成でよく演奏されていました。ジャズミュージシャンたちは、この楽器だけの部分を1周で終わらせずに何周も何周も繰り返し、そこでアドリブを繰り広げていったのです。
ジャズミュージシャンたちがスタンダードを演奏するときの一曲の構成は大まかに次のようになります。まず、曲に入る前の序奏として、4小節か8小節程度、曲の終わりの部分やお決まりのイントロを演奏します(ない場合もあります)。その後、「前(まえ)テーマ」と呼ばれる部分が始まります。ここでは、たいてい1周か2周、その曲のメロディを演奏します。そのあとが「ソロ」です。元になった曲を変奏する形で、それぞれの奏者が順番にアドリブソロを演奏します。たとえば、サックス、ピアノ、ベース、ドラムスの4人で演奏しているのであれば、始めにサックスがソロを吹き、もういいかなと思ったらピアノに受け渡し、ピアノソロも終わったら次にベースソロ、という順に進むことが多いです。この間もずっと、1周32小節の曲であればその32小節をグルグルと繰り返しているという形です。ドラムのソロにあたる部分は、ドラム以外とドラムとの掛け合いによる「バース」(bars、小節(bar)の複数形)と呼ばれるやり方をすることが多いですが、この間も1周32小節の形式は守られます。そして最後にようやくメロディを1周演奏して(「後(あと)テーマ」と呼ばれます)、短いエンディングを付けて一曲が終わります。
このように、ジャズのアドリブソロとは、あくまで元の曲の変奏を何周も何周もやっているものだと言えます。この変奏を行うときに指針となるのが、コード進行です。
学校の音楽の授業で、CM7(Cメジャーセブンス)やFm7(Fマイナーセブンス)などについて教わったでしょうか?コード(=和音)とは、異なる高さの音が同時になってできる音のことです。もちろんそのようなものは膨大な数考えられますが、各音の音名と一番低い音(ルート)とに着目して分類し名前を付けたものが、先述したCM7のような「コードネーム」です。メロディとコードネームだけが書かれた譜面を「リードシート」と呼びますが、ジャズミュージシャンたちはこのリードシートだけを見て、自分が演奏するべき役割(低音を支えるのか、メロディを吹くのか、中音域で和音を弾くのか、など)を考え、演奏していきます。
ところで、コード進行は思った以上に曖昧で、また自由な概念です。まず、同じ曲でも複数のコード進行が存在する場合があります。オーケストラの曲として書かれた原曲の段階で、アレンジャーの遊び心からバリエーションが生まれている場合もありますし、後世のミュージシャンがメロディに合う他のコード進行を持ってきて演奏し(リハーモナイゼーションと呼びます)、それが広まったものもあります。また、異なる曲どうしで共通するコード進行を見つけ、メロディやアレンジのアイデアを引用するということもよく行われます。これは、コードネームが記号であることの利点でしょう。
コードネームは、音楽の様々な要素(音色、音量、旋律の動きなど)を捨象して抽出された記号ですが、むしろそれを介して様々な音楽が生まれ花開いているとも言えます。そこにはパズル的な面白さや、一見異なるものに共通点を見出すという数学的思考がふんだんに隠れています。私の身の回りを見ても、数学とジャズの両方に魅力を感じる人は多いようです。みなさんも是非ジャズの世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。最後に、今回は紙面の都合もありコード進行という音の高さに関する話に終始しましたが、ジャズにはそれ以上に大切なリズムの要素もあることだけは書き添えておきます。
★冬期講習講座紹介
2025年11月30日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
講習開講まで3週間を切りました!
現時点で締切となっている講座はございませんが、少人数授業のため最も多くても定員は20名ほどです。
情報科学はさらに少ない10名程度となっておりますので、ご興味のある方はお早めにお申込みください。
講座詳細についてはこちらからご覧ください。
それでは、冬期講習の講座紹介をしていきたいと思います♪
№1【英語】科学的であるとはどういうことか?~科学哲学入門~
12月25日(木)~12月28日(日)17:30~20:40
【内容】第1講:科学と疑似科学、第2講:科学革命、第3講:科学的実在論と反実在論、第4講:科学と宗教
受講目安:主な対象学年は中3生~高3生としますが、この分野に興味がある中高生の方であればどなたでも歓迎いたします。
K会の英語講座は「英語でさまざまなことを学ぶ」ことが特徴です。
扱う英文は単語や文法を覚えるための文章ではなく、読み物として面白いこと、そしてみなさんに新たな発見を与えてくれることを重視しています。
たとえば第4講で扱う科学と宗教の話では、進化論を扱います。
みなさんは、社会で最古の人間サヘラントロプス(年代によってはアウストラロピテクス)を習いましたか?
恐らく多くの方は特別に疑問を持たず、私たち人間が猿人、原人、旧人、新人(ホモ・サピエンス)と進化してきたことを受け入れたはずです。
一方で、2019年にアメリカで行われた調査では「人間は神様が作ったもの」と考えている人が4割に上ることが分かりました。
人間は「進化」して今の姿になったのではなく、「神様が作った(最初から人間は人間の姿をしている)」と考えているということです。少し意外に感じませんか?
こうした内容がかかれた英文は中高生のみなさんにとって少し難しいかもしれません。しかし、骨のある文章を辞書なども使いながら4日間じっくり読みこんでいくうちに自然と読解力はついていきます。
科学哲学は耳慣れないものかもしれませんが、それほど敷居の高いものではありません。
たとえば人間を、進化したのではなく「神が人を作った」と考えるのは科学的でしょうか。科学的でないとするならばその根拠は何でしょうか。
科学的でない理由を「証明(再現)ができないからだ」と考えた場合、それは全ての科学的ではないものに当てはまるでしょうか。
言い換えれば、科学的なものは全て「証明」できるものなのでしょうか。少し考えてみてください。
科学哲学とは、このように科学について考える学問です。科学を科学たらしめているものは何か。この講座で考えてみませんか?
英語の読解力をつけたい方から、哲学を楽しみたい方まで幅広い方のご受講をお待ちしております!
お申し込みはこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581(【受付時間】火~土曜日 13:00-19:00)
講習開講まで3週間を切りました!
現時点で締切となっている講座はございませんが、少人数授業のため最も多くても定員は20名ほどです。
情報科学はさらに少ない10名程度となっておりますので、ご興味のある方はお早めにお申込みください。
講座詳細についてはこちらからご覧ください。
それでは、冬期講習の講座紹介をしていきたいと思います♪
№1【英語】科学的であるとはどういうことか?~科学哲学入門~
12月25日(木)~12月28日(日)17:30~20:40
【内容】第1講:科学と疑似科学、第2講:科学革命、第3講:科学的実在論と反実在論、第4講:科学と宗教
受講目安:主な対象学年は中3生~高3生としますが、この分野に興味がある中高生の方であればどなたでも歓迎いたします。
K会の英語講座は「英語でさまざまなことを学ぶ」ことが特徴です。
扱う英文は単語や文法を覚えるための文章ではなく、読み物として面白いこと、そしてみなさんに新たな発見を与えてくれることを重視しています。
たとえば第4講で扱う科学と宗教の話では、進化論を扱います。
みなさんは、社会で最古の人間サヘラントロプス(年代によってはアウストラロピテクス)を習いましたか?
恐らく多くの方は特別に疑問を持たず、私たち人間が猿人、原人、旧人、新人(ホモ・サピエンス)と進化してきたことを受け入れたはずです。
一方で、2019年にアメリカで行われた調査では「人間は神様が作ったもの」と考えている人が4割に上ることが分かりました。
人間は「進化」して今の姿になったのではなく、「神様が作った(最初から人間は人間の姿をしている)」と考えているということです。少し意外に感じませんか?
こうした内容がかかれた英文は中高生のみなさんにとって少し難しいかもしれません。しかし、骨のある文章を辞書なども使いながら4日間じっくり読みこんでいくうちに自然と読解力はついていきます。
科学哲学は耳慣れないものかもしれませんが、それほど敷居の高いものではありません。
たとえば人間を、進化したのではなく「神が人を作った」と考えるのは科学的でしょうか。科学的でないとするならばその根拠は何でしょうか。
科学的でない理由を「証明(再現)ができないからだ」と考えた場合、それは全ての科学的ではないものに当てはまるでしょうか。
言い換えれば、科学的なものは全て「証明」できるものなのでしょうか。少し考えてみてください。
科学哲学とは、このように科学について考える学問です。科学を科学たらしめているものは何か。この講座で考えてみませんか?
英語の読解力をつけたい方から、哲学を楽しみたい方まで幅広い方のご受講をお待ちしております!
お申し込みはこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581(【受付時間】火~土曜日 13:00-19:00)
★冬期セミナーのご案内★
2025年11月15日 更新
中高生とその保護者の方を対象とした冬期セミナーのお知らせです!
『広がる言語解読の世界―言語学オリンピックに挑戦―』
11月30日(日)10:00~12:00
講演者:小林 剛士
講演案内はこちらから
みなさんは言語を解読したことがありますか?
世界では6000~8000の言語が話されていると言われています。みなさんの知らない未知の言語がたくさんあるのです。
たとえばワルピリ語をご存じでしょうか。オーストラリアの先住民族の言語の一つで、約2000~3000人の人々がこの言語を使用しています。
言語を解読すると聞くと難しく感じるかもしれませんが、決して中高生のみなさんにできないことはありません!
試しにワルピリ語を解読してみましょう!
以下にワルピリ語の文とその日本語訳があります。
●Kurdu ka wangkami.(子どもが話す。)
●Kurdungku ka marlu yampimi.(子どもがカンガルーを放っておく。)
●Kirda kula wangkaja.(父が話さなかった。)
●Karnta kulaka parnkami.(女が走らない。)
●Kirdangku kurdu yampija.(父が子どもを放っておいた。)
1.「子ども」を意味する語を答えてください。
2.以下を日本語に訳してください。
Marlu parnkaja.
3. 以下をワルピリ語に訳してください。
カンガルーが子どもを放っておかない。
出典:パズルで解く世界の言語
解答はこちらから
いかがでしたか?
日本言語学オリンピックは中高生の方だけでなく、保護者の方もオープン参加ができる珍しい大会です!
少しでも言語解読の世界に興味をもってくださった方は、お友達同士、親子でぜひ気軽に本セミナーにお越しください。
イベント詳細・お申し込みはこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
『広がる言語解読の世界―言語学オリンピックに挑戦―』
11月30日(日)10:00~12:00
講演者:小林 剛士
講演案内はこちらから
みなさんは言語を解読したことがありますか?
世界では6000~8000の言語が話されていると言われています。みなさんの知らない未知の言語がたくさんあるのです。
たとえばワルピリ語をご存じでしょうか。オーストラリアの先住民族の言語の一つで、約2000~3000人の人々がこの言語を使用しています。
言語を解読すると聞くと難しく感じるかもしれませんが、決して中高生のみなさんにできないことはありません!
試しにワルピリ語を解読してみましょう!
以下にワルピリ語の文とその日本語訳があります。
●Kurdu ka wangkami.(子どもが話す。)
●Kurdungku ka marlu yampimi.(子どもがカンガルーを放っておく。)
●Kirda kula wangkaja.(父が話さなかった。)
●Karnta kulaka parnkami.(女が走らない。)
●Kirdangku kurdu yampija.(父が子どもを放っておいた。)
1.「子ども」を意味する語を答えてください。
2.以下を日本語に訳してください。
Marlu parnkaja.
3. 以下をワルピリ語に訳してください。
カンガルーが子どもを放っておかない。
出典:パズルで解く世界の言語
解答はこちらから
いかがでしたか?
日本言語学オリンピックは中高生の方だけでなく、保護者の方もオープン参加ができる珍しい大会です!
少しでも言語解読の世界に興味をもってくださった方は、お友達同士、親子でぜひ気軽に本セミナーにお越しください。
イベント詳細・お申し込みはこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
━【現代数学の視座と眺望№8(K会元数学科講師:立原礼也) 】━
2025年11月12日 更新
━【現代数学の視座と眺望№8 (K会元数学科講師:立原礼也) 】━
★「現代数学」、つまり大雑把には「大学の数学科レベルの数学」は、中高で習う数学と地続きに繋がっていながらも、様々な面で、全く新しい考え方に基づくものでもあります。筆者が数学を専攻することに決めたのも、この新しくも自然な考え方の数々に魅了されてのことでした。このコラムでは、現代数学におけるものの見方=「視座」、そしてそれによるものの見え方=「眺望」の解説を通じ、現代数学の魅力の一端をお伝えしていきます★
抽象数学の道のり
読者の皆さん、こんにちは。
K会数学科元講師の立原礼也と申します。
第6回から第7回にかけては、本連載の趣旨から少し外れて、数学の抽象性と、そこから生じる難しさ、それに対してどう向き合うべきかについての提案、といったテーマを議論しました。現代数学においては、この抽象化が更に激しいものとなって学習者のハードルとなってしまったりもするわけで、だから前回のような記事を書いてみたのですが、もちろん数学者もむやみやたらに抽象化をしているわけではなく、計り知れない大きな恩恵があるからこそ抽象化の道を進むのです。この「恩恵」については、本連載においても、例えば第5回の、整数論における虚数の活躍を論じた回などで紹介しています。
(そもそも虚数という概念自体もある種の抽象化の上に成り立つものですし、また、そういった文脈の整数論では「環論」という抽象理論が必要になることもその文脈で触れました。)あるいは第3回で紹介した、現代数学の最重要概念の一つである「同型」も、抽象数学の視点に立って初めて成り立つものです。
繰り返しになりますが、抽象化の意義は計り知れないほど大きなものであって、その実例も枚挙にいとまがありません。第8回となる今回は、これまでのいくつかの記事で個別の事例やその意義について掘り下げたのとは対照的に、そうした具体的な内容は軽く触れるに留めて、俯瞰的に、ダイジェスト的に、抽象数学の道のりを皆さんにご紹介することを試みたいと思います。筆者なりの観点から、したがって筆者の専門分野等の個人的事情も色濃く反映された形のダイジェストにはなるのですが、どうかお付き合いください。
さて、これは以前の記事でも指摘したことですが、抽象化は、現代数学という以前に、そもそも数学という学問そのものの出発点でもあります。何しろ、数というのがまず抽象的です。3個のリンゴや3羽の鳥が、「3」という抽象化によって統一的に記述されるようになるのです。整数ではない実数や、またゼロや負の数も考えるなら、更に抽象的な認識が必要になりますが、現代ではそういった数も日常生活レベルでも不可欠の存在となっていますね。
個々の数がそもそも抽象的ですが、更に抽象化を一歩進めると、文字式の概念に辿り着きます。文字を使うことで、無限に沢山存在する数たちを同時的に取り扱う/考察することが可能になります。例えば(a+b)の2乗=(aの2乗)+2ab+(bの2乗)という中学で習う関係式がありますが、これはaやbにどんな数を当てはめても正しいということになるわけです。aに7を、bに16を当てはめれば、「(7+16)の2乗=(7の2乗)+2×7×16+(16の2乗)」が具体的な計算をしなくてもわかってしまう、といった具合です。こうした取り扱いによってはじめて、すべての数に通用する普遍的な法則を見出すための枠組みが得られるのですから、その意義は明らかです。更に、文字式の計算が実生活上の問題へのアプローチにも応用可能なことは、前回記事までに話題に挙げた中学数学レベルの「方程式の文章題」の例にも見られます。
ただでさえ抽象的な個々の数を抽象化して「文字式」の概念に到達しましたが、更に俯瞰的な視点で見ると、「数たち」も「文字式たち」も、それぞれ1つの計算体系をなしています。つまりこういうことです。数どうしは足し算や掛け算ができて、計算結果も数が出てきます。当たり前のことです。そして、ここで言いたいのは、文字式たちもそういうものになっている、ということです。
ここでは本質を損ねずに議論の複雑度を下げるために、xという文字しか出てこない多項式に絞って考えてみましょう。するとそういうものは、やはり、足し算や掛け算で閉じた計算体系をなしているのです。例えば、(xの2乗)+3x+2という式と、3(xの2乗)-9x+5という式がありますが、これを足すと4(xの2乗)-6x+7という式になって、同じようにxという文字しか出てこない多項式になります。掛け算は大変なので省略しますが、ともかくxという文字しか出てこない多項式を、足したり掛けたりしても、xという文字しか出てこない多項式になるのです。これも、一見ややこしいですが、当たり前のことです。
ちなみに、ちょっと横道にそれますが、4xや-2(xの3乗)などといった単項式や、xすら出てこない定数なども、多項式と考えます。ですから例えば、多項式(xの2乗)+3xと多項式4(xの2乗)-3xを足すと5(xの2乗)になってしまって、単項式になってしまいますが、単項式も多項式の一種なので問題ありません。これは、正方形が長方形でもあり、ひし形でもあるのと同じことです。日常生活では正方形のことを長方形と言ったりひし形と言ったりしたら変な人かもしれませんが、数学という学問の上ではそれで正しいのです。日常感覚に配慮した例外規定などは設けずに、統一的に言葉遣いを定めた方が、全ての数学的議論が上手くいきます。考えてみると、言葉遣いに関するこういう態度も、抽象化の姿勢と深く関連したものかもしれません。
話を戻しましょう。上述のような。「足し算や掛け算ができる計算体系」のことを「環」と呼びます。(正確には「単位的可換環」を想定しています。)(本当は、引き算もできるとか、分配法則があるとか、厳密に書くと面倒なのですが、今回はそういったことには全部目を瞑ることにしています。)例えば、「整数たち」も環の一例です(整数と整数の和や積は整数になることに注意しましょう)。「有理数たち」も、「実数たち」も「複素数たち」も環の一例です。また、更に上で扱った「(文字xに関する)実数係数1変数多項式たち」も環の一例です。ほかにも沢山の例があります。ここで、「整数たち」という環と「有理数たち」という環は、互いに深く関連してはいるものの、独立して存在する、全く異なった環であることに注意しておきましょう。
かなりややこしいですが、ついてきてください。無限に沢山存在する数たちを同時的に考察するために文字を導入したのと似ています。様々な計算体系を同時的に取り扱う/考察するために、環という概念があるのです。例えば、「整数たち」という環では「素因数分解」という操作ができ(連載第5回をご参照ください)、「実数係数1変数多項式たち」という環では「因数分解」という操作ができます。これらは名前は似ていても違う概念ですが、環論の枠組みでは「既約分解」として同時的/統一的な理解が可能です。
なお、既約分解の一意性(本質的に一通りの方法しかないこと)は環によって成り立ったり成り立たなかったりするのですが、「整数たち」「実数係数1変数多項式たち」に関して言えば、「ユークリッドの互除法」を活用することで一意性が成り立つことを証明できます。一意性の成立の背景にあるこのようなカラクリも、環論では、「ユークリッド整域は一意分解整域である」という定理として抽象化して理解することができます。これだけだと「簡単なことを難しく言っただけ」にも見えてしまいますが、そうではありません。例えば、この事実を活用することで、連載第5回に述べた「ガウス整数の環でもそのまま普通の整数論のようなことができる」という事実が明らかになるのです。
さて、環論では、個別の環を考えるだけでなく、それらの間の相互関係に着目することが非常に大切になります。ごく簡単な例ですと、「整数たち」という環と「有理数たち」という環は全く異なる別々の環ですが、「前者は後者に含まれている」という関係性があることも大切です。もっと複雑な関係性としては例えば、「実数係数1変数多項式たち」と「実数たち」の間には、「変数に特定の値を代入する」という関連付けを行うことも可能です。(きちんと厳密に扱うなら、「環準同型」という概念を用いることになります。)
この「対象の相互関係に着目する」ことの重要性は環論に限らず、数学の様々な分野について言えることです。筆者の専門性が代数学に近いこともあり、ここまで代数中心に話を進めてきましたが、例えば幾何学では、図形の抽象化として「位相空間」といったものを考えます。するとやはり、個々の位相空間を独立して考えるだけではなくて、位相空間同士の相互関係を考えるのです。このように、数学の理論がもつ典型的な構造として、「様々な対象があり、それらの間の様々な関連付け方がある」という構造が見いだされます。
これを抽象化すると、「圏」という概念に至ります。先ほど、計算体系の抽象化として環に至ったわけですが、今度は数学の理論体系を抽象化して圏に辿り着くのです。実に大胆なことだと思います。こうして、圏の具体例として、群論の理論体系を反映した「群の圏」、環論の理論体系を反映した「環の圏」、そして位相空間論の理論体系を反映した「位相空間の圏」などが生じるわけです。もちろん、圏論の理論体系を反映した「圏の圏」を考えることも可能で、このような一見冗談のようにも見えそうな考察は(筆者は専門外ですが)「高次圏論」といった話題へとつながってゆき、段々と最先端の話題になってきます。そこではトポロジー(図形の連続変形を扱う幾何学)に端を発する、ホモトピーの考え方が非常に重要になるようです。数学理論の構造を抽象化した枠組みを考えると、それ自体が幾何学的な考察対象になるのは、興味深い展開だと思います。
さて、「環の圏」と圏同値な圏としては「アフィンスキームの圏」が挙げられます。「圏同値」というのは非常に大まかには「圏の同型」のようなもので(同型については第3回記事をご参照ください)、つまり大雑把に言えば、環論とアフィンスキームの理論は大体等価だということです。実は、アフィンスキームの概念はこの圏同値が成り立つように定義するので、この圏同値そのものは特に驚くべきことではないのですが、大切なのはアフィンスキームは位相空間などとも関連が深く、十分に幾何学的に理解が可能な対象だということです。
多くの人は、例えば整数の考察をするときに、図形を思い浮かべたりはしないと思います。しかし筆者の場合、環の考察をするときには対応するアフィンスキームの幾何描像を思い浮かべることはしばしばあり、「整数たち」の環でも例外ではありません。流石に大学入試の整数問題のような場面ですとこれが直接役に立つことはほぼありません。しかし例えば「中国剰余定理」と呼ばれる重要な定理(補足参照)がほとんど当たり前になってしまったりと、アフィンスキームの幾何学は実に晴れやかな眺望をもたらしてくれる、ひとつの視座として非常に優れたものなのです。
アフィンスキームの幾何学の観点からは、中国剰余定理は、まるで「図形Cが交わらない2つのパーツAとBに分けられるとき、AとBを並べたものが図形Cだ」と言っているかのような感じで、直感的にはほとんど同義反復のようになります。直感で処理した部分を更に厳密に証明しようとすると、流石に少し考えるべきことは出てくるのですが、それは簡単にクリアできて、結局よく知られた証明が自然に現れます。つまりどういうことかというと、よく知られた証明に、自然と幾何学的な意味が付くのです。そして、どんな環でも、なんと「整数たち」の環すらも幾何学的にみることができるという事実は、まさに筆者の専門分野である数論幾何学の1つの出発点ともなります。
まだまだどんどん書き進めてゆきたいところなのですが、字数がずいぶん多くなってしまいました。ちょっと唐突な終わり方ですが、今回はここまでにしておきましょう。蛇足ながら、数論幾何学にも色々ありまして、その中でも筆者の専門に当たる遠アーベル幾何学については第4回記事で平易な解説を試みていますので、そちらも併せてぜひご覧いただけましたら幸いです。
-----
(補足)中国剰余定理
2つの整数mとnの素因数分解に共通の素数が全く現れないとき、mとnは互いに素であると言います。例えば、12と21は互いに素ではありません。なぜなら、素因数分解してみると12=2×2×3、21=3×7で、どちらにも3という共通の素数が現れてしまうからです。これに対して、25の素因数分解は25=5×5なので、12と25や21と25は互いに素です。また、素数は最初から素因数分解されていると考えるので、異なる素数同士は互いに素です。
実は、mとnが互いに素だと、「mで割った余り」と「nで割った余り」の情報から、「積mnで割った余り」の情報が確定します。これが中国剰余定理です。例えば、m=12, n=25で考えると(12と25が互いに素であることに注意しましょう)、積mnは300なので、「12で割った余り」と「25で割った余り」の情報から「300で割った余り」の情報が確定する、ということです。しかし、「確定する」というのは少し不正確な言葉遣いなので、以下に具体例を通じてもう少し正確に説明しましょう。
まず、中国剰余定理の前に、もっと当たり前の前提を確認します。例えば、ある整数を300で割った余りが39だとしましょう。つまり、その数は300×整数+39と表せるということです。300というのは(もともと12×25として計算したのですから当たり前のことですが)12で割り切れます。ですから300×整数+39の形に表せる数を12で割った余りは、39を12で割った余りと一緒で、3になります。同じように考えると、300×整数+37の形で表せる数を25で割った余りは14になります。
まとめると、300で割って39余る整数は、12で割ると3余り、25で割ると14余るということです。同じようにして、「300で割った余り」の情報から、「12で割った余り」の情報と、「25で割った余り」の情報を確定させることができます。更に同じように考えれば、「mnを割った余り」の情報からは「mで割った余り」の情報と「nで割った余り」の情報が確定するのです。ここまでは、特別な工夫は必要ないことで、整数の計算に慣れている人にとっては当たり前のことです。何しろ、ここまでは、mとnが互いに素でなくても問題ありません。
当たり前でないことは何かというと、mとnが互いに素のときに限っては、逆方向もできるということです。これが中国剰余定理です。つまりどういうことかというと、「12で割った余りが3」で「25で割った余りが14」という情報から、「300で割った余りが39」ということが完全に確定してしまうのです。「300で割った余りが77の数も、39の場合と同じく、12で割ると3余って25で割ると14余る」のような事故は決しておきない、ということです。それだけではありません。必ず対応する「300で割った余り」が存在するということも言えます。「12で割った余りがa」「25で割った余りがb」このaに読者は好きなように0以上11以下の値を当てはめてください。更にbにも0以上24以下の値も当てはめてください。読者がどんなふうにaとbに値を当てはめても、それに対応する300で割った余りが必ずただひとつあるのです。読者がaに11を当てはめてbに7を当てはめたなら、対応する300で割った余りは107になります(確かめてみてください)。
実は中国剰余定理の対応は具体的に計算することができます。上で「a=11, b=7なら、107が対応する」と述べましたが、0から299までしらみつぶしに調べたりしなくても、ちょっとした計算手続きで11と7から107を導くことができるのです。実は、中国剰余定理のスタンダードな証明を深く理解していれば、その証明に計算手続きが含まれていることがわかります。なお、当記事の本文との関連で言うと、この証明中の計算手続きのところに、「1の分割」と呼ばれる幾何的な解釈が付くのです。「1の分割」は多様体論などで重要な役割を果たす幾何の概念ですが、そのアフィンスキームにおけるある類似が、中国剰余定理の証明に幾何学的な理解を提供してくれるのです。
ちなみに、中国剰余定理は、「整数たち」の環に限らず、あらゆる単位的可換環で定式化して証明することができます。それにも全く同様に、アフィンスキーム上の1の分割による幾何学的な意味がつきます。素晴らしいことです。なお。K会現代数学コース『集合と代数系』における中国剰余定理の証明は、アフィンスキームは出てきませんが、この幾何学的な理解を反映して整理したものになっています。
-----
(意欲ある読者に向けた、答えのない演習問題)
補足の内容に関する問題です。中国剰余定理の証明を調べてよく検討し、そこから「計算手続き」を抽出してみてください。それを使って、いろいろなaとbに対して、12で割った余りがaで25で割った余りがbの数を300で割った余りを求めてみてください。(ヒント:まず「a=1でb=0の場合」と「a=0でb=1の場合」に求める。それを上手く使えば他の場合もすぐに計算できる。)
★「現代数学」、つまり大雑把には「大学の数学科レベルの数学」は、中高で習う数学と地続きに繋がっていながらも、様々な面で、全く新しい考え方に基づくものでもあります。筆者が数学を専攻することに決めたのも、この新しくも自然な考え方の数々に魅了されてのことでした。このコラムでは、現代数学におけるものの見方=「視座」、そしてそれによるものの見え方=「眺望」の解説を通じ、現代数学の魅力の一端をお伝えしていきます★
抽象数学の道のり
読者の皆さん、こんにちは。
K会数学科元講師の立原礼也と申します。
第6回から第7回にかけては、本連載の趣旨から少し外れて、数学の抽象性と、そこから生じる難しさ、それに対してどう向き合うべきかについての提案、といったテーマを議論しました。現代数学においては、この抽象化が更に激しいものとなって学習者のハードルとなってしまったりもするわけで、だから前回のような記事を書いてみたのですが、もちろん数学者もむやみやたらに抽象化をしているわけではなく、計り知れない大きな恩恵があるからこそ抽象化の道を進むのです。この「恩恵」については、本連載においても、例えば第5回の、整数論における虚数の活躍を論じた回などで紹介しています。
(そもそも虚数という概念自体もある種の抽象化の上に成り立つものですし、また、そういった文脈の整数論では「環論」という抽象理論が必要になることもその文脈で触れました。)あるいは第3回で紹介した、現代数学の最重要概念の一つである「同型」も、抽象数学の視点に立って初めて成り立つものです。
繰り返しになりますが、抽象化の意義は計り知れないほど大きなものであって、その実例も枚挙にいとまがありません。第8回となる今回は、これまでのいくつかの記事で個別の事例やその意義について掘り下げたのとは対照的に、そうした具体的な内容は軽く触れるに留めて、俯瞰的に、ダイジェスト的に、抽象数学の道のりを皆さんにご紹介することを試みたいと思います。筆者なりの観点から、したがって筆者の専門分野等の個人的事情も色濃く反映された形のダイジェストにはなるのですが、どうかお付き合いください。
さて、これは以前の記事でも指摘したことですが、抽象化は、現代数学という以前に、そもそも数学という学問そのものの出発点でもあります。何しろ、数というのがまず抽象的です。3個のリンゴや3羽の鳥が、「3」という抽象化によって統一的に記述されるようになるのです。整数ではない実数や、またゼロや負の数も考えるなら、更に抽象的な認識が必要になりますが、現代ではそういった数も日常生活レベルでも不可欠の存在となっていますね。
個々の数がそもそも抽象的ですが、更に抽象化を一歩進めると、文字式の概念に辿り着きます。文字を使うことで、無限に沢山存在する数たちを同時的に取り扱う/考察することが可能になります。例えば(a+b)の2乗=(aの2乗)+2ab+(bの2乗)という中学で習う関係式がありますが、これはaやbにどんな数を当てはめても正しいということになるわけです。aに7を、bに16を当てはめれば、「(7+16)の2乗=(7の2乗)+2×7×16+(16の2乗)」が具体的な計算をしなくてもわかってしまう、といった具合です。こうした取り扱いによってはじめて、すべての数に通用する普遍的な法則を見出すための枠組みが得られるのですから、その意義は明らかです。更に、文字式の計算が実生活上の問題へのアプローチにも応用可能なことは、前回記事までに話題に挙げた中学数学レベルの「方程式の文章題」の例にも見られます。
ただでさえ抽象的な個々の数を抽象化して「文字式」の概念に到達しましたが、更に俯瞰的な視点で見ると、「数たち」も「文字式たち」も、それぞれ1つの計算体系をなしています。つまりこういうことです。数どうしは足し算や掛け算ができて、計算結果も数が出てきます。当たり前のことです。そして、ここで言いたいのは、文字式たちもそういうものになっている、ということです。
ここでは本質を損ねずに議論の複雑度を下げるために、xという文字しか出てこない多項式に絞って考えてみましょう。するとそういうものは、やはり、足し算や掛け算で閉じた計算体系をなしているのです。例えば、(xの2乗)+3x+2という式と、3(xの2乗)-9x+5という式がありますが、これを足すと4(xの2乗)-6x+7という式になって、同じようにxという文字しか出てこない多項式になります。掛け算は大変なので省略しますが、ともかくxという文字しか出てこない多項式を、足したり掛けたりしても、xという文字しか出てこない多項式になるのです。これも、一見ややこしいですが、当たり前のことです。
ちなみに、ちょっと横道にそれますが、4xや-2(xの3乗)などといった単項式や、xすら出てこない定数なども、多項式と考えます。ですから例えば、多項式(xの2乗)+3xと多項式4(xの2乗)-3xを足すと5(xの2乗)になってしまって、単項式になってしまいますが、単項式も多項式の一種なので問題ありません。これは、正方形が長方形でもあり、ひし形でもあるのと同じことです。日常生活では正方形のことを長方形と言ったりひし形と言ったりしたら変な人かもしれませんが、数学という学問の上ではそれで正しいのです。日常感覚に配慮した例外規定などは設けずに、統一的に言葉遣いを定めた方が、全ての数学的議論が上手くいきます。考えてみると、言葉遣いに関するこういう態度も、抽象化の姿勢と深く関連したものかもしれません。
話を戻しましょう。上述のような。「足し算や掛け算ができる計算体系」のことを「環」と呼びます。(正確には「単位的可換環」を想定しています。)(本当は、引き算もできるとか、分配法則があるとか、厳密に書くと面倒なのですが、今回はそういったことには全部目を瞑ることにしています。)例えば、「整数たち」も環の一例です(整数と整数の和や積は整数になることに注意しましょう)。「有理数たち」も、「実数たち」も「複素数たち」も環の一例です。また、更に上で扱った「(文字xに関する)実数係数1変数多項式たち」も環の一例です。ほかにも沢山の例があります。ここで、「整数たち」という環と「有理数たち」という環は、互いに深く関連してはいるものの、独立して存在する、全く異なった環であることに注意しておきましょう。
かなりややこしいですが、ついてきてください。無限に沢山存在する数たちを同時的に考察するために文字を導入したのと似ています。様々な計算体系を同時的に取り扱う/考察するために、環という概念があるのです。例えば、「整数たち」という環では「素因数分解」という操作ができ(連載第5回をご参照ください)、「実数係数1変数多項式たち」という環では「因数分解」という操作ができます。これらは名前は似ていても違う概念ですが、環論の枠組みでは「既約分解」として同時的/統一的な理解が可能です。
なお、既約分解の一意性(本質的に一通りの方法しかないこと)は環によって成り立ったり成り立たなかったりするのですが、「整数たち」「実数係数1変数多項式たち」に関して言えば、「ユークリッドの互除法」を活用することで一意性が成り立つことを証明できます。一意性の成立の背景にあるこのようなカラクリも、環論では、「ユークリッド整域は一意分解整域である」という定理として抽象化して理解することができます。これだけだと「簡単なことを難しく言っただけ」にも見えてしまいますが、そうではありません。例えば、この事実を活用することで、連載第5回に述べた「ガウス整数の環でもそのまま普通の整数論のようなことができる」という事実が明らかになるのです。
さて、環論では、個別の環を考えるだけでなく、それらの間の相互関係に着目することが非常に大切になります。ごく簡単な例ですと、「整数たち」という環と「有理数たち」という環は全く異なる別々の環ですが、「前者は後者に含まれている」という関係性があることも大切です。もっと複雑な関係性としては例えば、「実数係数1変数多項式たち」と「実数たち」の間には、「変数に特定の値を代入する」という関連付けを行うことも可能です。(きちんと厳密に扱うなら、「環準同型」という概念を用いることになります。)
この「対象の相互関係に着目する」ことの重要性は環論に限らず、数学の様々な分野について言えることです。筆者の専門性が代数学に近いこともあり、ここまで代数中心に話を進めてきましたが、例えば幾何学では、図形の抽象化として「位相空間」といったものを考えます。するとやはり、個々の位相空間を独立して考えるだけではなくて、位相空間同士の相互関係を考えるのです。このように、数学の理論がもつ典型的な構造として、「様々な対象があり、それらの間の様々な関連付け方がある」という構造が見いだされます。
これを抽象化すると、「圏」という概念に至ります。先ほど、計算体系の抽象化として環に至ったわけですが、今度は数学の理論体系を抽象化して圏に辿り着くのです。実に大胆なことだと思います。こうして、圏の具体例として、群論の理論体系を反映した「群の圏」、環論の理論体系を反映した「環の圏」、そして位相空間論の理論体系を反映した「位相空間の圏」などが生じるわけです。もちろん、圏論の理論体系を反映した「圏の圏」を考えることも可能で、このような一見冗談のようにも見えそうな考察は(筆者は専門外ですが)「高次圏論」といった話題へとつながってゆき、段々と最先端の話題になってきます。そこではトポロジー(図形の連続変形を扱う幾何学)に端を発する、ホモトピーの考え方が非常に重要になるようです。数学理論の構造を抽象化した枠組みを考えると、それ自体が幾何学的な考察対象になるのは、興味深い展開だと思います。
さて、「環の圏」と圏同値な圏としては「アフィンスキームの圏」が挙げられます。「圏同値」というのは非常に大まかには「圏の同型」のようなもので(同型については第3回記事をご参照ください)、つまり大雑把に言えば、環論とアフィンスキームの理論は大体等価だということです。実は、アフィンスキームの概念はこの圏同値が成り立つように定義するので、この圏同値そのものは特に驚くべきことではないのですが、大切なのはアフィンスキームは位相空間などとも関連が深く、十分に幾何学的に理解が可能な対象だということです。
多くの人は、例えば整数の考察をするときに、図形を思い浮かべたりはしないと思います。しかし筆者の場合、環の考察をするときには対応するアフィンスキームの幾何描像を思い浮かべることはしばしばあり、「整数たち」の環でも例外ではありません。流石に大学入試の整数問題のような場面ですとこれが直接役に立つことはほぼありません。しかし例えば「中国剰余定理」と呼ばれる重要な定理(補足参照)がほとんど当たり前になってしまったりと、アフィンスキームの幾何学は実に晴れやかな眺望をもたらしてくれる、ひとつの視座として非常に優れたものなのです。
アフィンスキームの幾何学の観点からは、中国剰余定理は、まるで「図形Cが交わらない2つのパーツAとBに分けられるとき、AとBを並べたものが図形Cだ」と言っているかのような感じで、直感的にはほとんど同義反復のようになります。直感で処理した部分を更に厳密に証明しようとすると、流石に少し考えるべきことは出てくるのですが、それは簡単にクリアできて、結局よく知られた証明が自然に現れます。つまりどういうことかというと、よく知られた証明に、自然と幾何学的な意味が付くのです。そして、どんな環でも、なんと「整数たち」の環すらも幾何学的にみることができるという事実は、まさに筆者の専門分野である数論幾何学の1つの出発点ともなります。
まだまだどんどん書き進めてゆきたいところなのですが、字数がずいぶん多くなってしまいました。ちょっと唐突な終わり方ですが、今回はここまでにしておきましょう。蛇足ながら、数論幾何学にも色々ありまして、その中でも筆者の専門に当たる遠アーベル幾何学については第4回記事で平易な解説を試みていますので、そちらも併せてぜひご覧いただけましたら幸いです。
-----
(補足)中国剰余定理
2つの整数mとnの素因数分解に共通の素数が全く現れないとき、mとnは互いに素であると言います。例えば、12と21は互いに素ではありません。なぜなら、素因数分解してみると12=2×2×3、21=3×7で、どちらにも3という共通の素数が現れてしまうからです。これに対して、25の素因数分解は25=5×5なので、12と25や21と25は互いに素です。また、素数は最初から素因数分解されていると考えるので、異なる素数同士は互いに素です。
実は、mとnが互いに素だと、「mで割った余り」と「nで割った余り」の情報から、「積mnで割った余り」の情報が確定します。これが中国剰余定理です。例えば、m=12, n=25で考えると(12と25が互いに素であることに注意しましょう)、積mnは300なので、「12で割った余り」と「25で割った余り」の情報から「300で割った余り」の情報が確定する、ということです。しかし、「確定する」というのは少し不正確な言葉遣いなので、以下に具体例を通じてもう少し正確に説明しましょう。
まず、中国剰余定理の前に、もっと当たり前の前提を確認します。例えば、ある整数を300で割った余りが39だとしましょう。つまり、その数は300×整数+39と表せるということです。300というのは(もともと12×25として計算したのですから当たり前のことですが)12で割り切れます。ですから300×整数+39の形に表せる数を12で割った余りは、39を12で割った余りと一緒で、3になります。同じように考えると、300×整数+37の形で表せる数を25で割った余りは14になります。
まとめると、300で割って39余る整数は、12で割ると3余り、25で割ると14余るということです。同じようにして、「300で割った余り」の情報から、「12で割った余り」の情報と、「25で割った余り」の情報を確定させることができます。更に同じように考えれば、「mnを割った余り」の情報からは「mで割った余り」の情報と「nで割った余り」の情報が確定するのです。ここまでは、特別な工夫は必要ないことで、整数の計算に慣れている人にとっては当たり前のことです。何しろ、ここまでは、mとnが互いに素でなくても問題ありません。
当たり前でないことは何かというと、mとnが互いに素のときに限っては、逆方向もできるということです。これが中国剰余定理です。つまりどういうことかというと、「12で割った余りが3」で「25で割った余りが14」という情報から、「300で割った余りが39」ということが完全に確定してしまうのです。「300で割った余りが77の数も、39の場合と同じく、12で割ると3余って25で割ると14余る」のような事故は決しておきない、ということです。それだけではありません。必ず対応する「300で割った余り」が存在するということも言えます。「12で割った余りがa」「25で割った余りがb」このaに読者は好きなように0以上11以下の値を当てはめてください。更にbにも0以上24以下の値も当てはめてください。読者がどんなふうにaとbに値を当てはめても、それに対応する300で割った余りが必ずただひとつあるのです。読者がaに11を当てはめてbに7を当てはめたなら、対応する300で割った余りは107になります(確かめてみてください)。
実は中国剰余定理の対応は具体的に計算することができます。上で「a=11, b=7なら、107が対応する」と述べましたが、0から299までしらみつぶしに調べたりしなくても、ちょっとした計算手続きで11と7から107を導くことができるのです。実は、中国剰余定理のスタンダードな証明を深く理解していれば、その証明に計算手続きが含まれていることがわかります。なお、当記事の本文との関連で言うと、この証明中の計算手続きのところに、「1の分割」と呼ばれる幾何的な解釈が付くのです。「1の分割」は多様体論などで重要な役割を果たす幾何の概念ですが、そのアフィンスキームにおけるある類似が、中国剰余定理の証明に幾何学的な理解を提供してくれるのです。
ちなみに、中国剰余定理は、「整数たち」の環に限らず、あらゆる単位的可換環で定式化して証明することができます。それにも全く同様に、アフィンスキーム上の1の分割による幾何学的な意味がつきます。素晴らしいことです。なお。K会現代数学コース『集合と代数系』における中国剰余定理の証明は、アフィンスキームは出てきませんが、この幾何学的な理解を反映して整理したものになっています。
-----
(意欲ある読者に向けた、答えのない演習問題)
補足の内容に関する問題です。中国剰余定理の証明を調べてよく検討し、そこから「計算手続き」を抽出してみてください。それを使って、いろいろなaとbに対して、12で割った余りがaで25で割った余りがbの数を300で割った余りを求めてみてください。(ヒント:まず「a=1でb=0の場合」と「a=0でb=1の場合」に求める。それを上手く使えば他の場合もすぐに計算できる。)
★本日から冬期講習のお申し込み受け付けがスタートします★
2025年10月21日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
本日10/21(火)13:00から冬期講習の受付がはじまります!
設置講座は数学・英語・情報・物理・化学・生物・地理・天文学・言語学の全19講座!
講座の詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/winter/kkai/curriculum/
この冬は天文学オリンピック直前対策講座が初開講します!
講座では過去問題を使いながら天文学特有の計算に慣れる練習や、データ解析の要素がある問題へのアプローチを学んでいきます。
講師は第16回国際天文学・天体物理学オリンピック日本代表の早川さんです。
試験のテクニックはもちろんですが、オリンピックの経験談や天文学の面白さなどもお伝えしていく予定ですのでお楽しみに!
また、『LaTeX入門~数学書を作ろう』という講座も初開講です!
LaTeXとは主に数式を含む本や論文を書くためのソフトウェアです。
中高生のみなさんには馴染みが無いかもしれませんが、大学で主に理工系の学部への進学を考えている方であれば知っておいて損のない知識です。
受講に際して特別な知識は必要ありません。
数式や化学式などを手書きではなく、文書作成ソフトを使って美しく書きたいという中学生の方から、理系の学部に進路が決まった高3生までどなたでも歓迎いたします!
▼講座のお申し込みは下記URLから
https://www.kawai-juku.ac.jp/winter/kkai/apply/
【お問合せ】
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00) ※お申し込みはWebから
本日10/21(火)13:00から冬期講習の受付がはじまります!
設置講座は数学・英語・情報・物理・化学・生物・地理・天文学・言語学の全19講座!
講座の詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/winter/kkai/curriculum/
この冬は天文学オリンピック直前対策講座が初開講します!
講座では過去問題を使いながら天文学特有の計算に慣れる練習や、データ解析の要素がある問題へのアプローチを学んでいきます。
講師は第16回国際天文学・天体物理学オリンピック日本代表の早川さんです。
試験のテクニックはもちろんですが、オリンピックの経験談や天文学の面白さなどもお伝えしていく予定ですのでお楽しみに!
また、『LaTeX入門~数学書を作ろう』という講座も初開講です!
LaTeXとは主に数式を含む本や論文を書くためのソフトウェアです。
中高生のみなさんには馴染みが無いかもしれませんが、大学で主に理工系の学部への進学を考えている方であれば知っておいて損のない知識です。
受講に際して特別な知識は必要ありません。
数式や化学式などを手書きではなく、文書作成ソフトを使って美しく書きたいという中学生の方から、理系の学部に進路が決まった高3生までどなたでも歓迎いたします!
▼講座のお申し込みは下記URLから
https://www.kawai-juku.ac.jp/winter/kkai/apply/
【お問合せ】
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00) ※お申し込みはWebから
★受付終了まであと3日!★
2025年10月19日 更新
イベントのお申し込みは12月21日(火)23:59まで!!
『円周率の秘密』
10月25日(土)14:00~16:00
講師:桝澤 海斗
イベント案内はこちらから
【よくあるご質問】
Q1:男女比はどれくらいですか?
A1:年によって異なりますが、2:1でやや男子生徒の方が多めです。
Q2:低学年ですが受講は可能ですか?
A2:学年で制限は設けておりません。分数・小数の計算、整数の性質(約数・倍数)図形の面積などについて理解されている方であれば学年を問わずご受講いただけます。
Q3:未就学児の弟・妹も一緒に連れていきたいのですが可能ですか。
A3:授業に参加することが難しい場合は控え室をご利用ください。教室の隣の部屋を保護者さまや小さなお子さまのための控え室としております。
Q4:当日必要なものはありますか?
A4:筆記用具をお持ちください。お持ちでない場合は貸し出しいたしますので、スタッフまでお声かけください。
Q5:申込期限を過ぎてしまいました。まだ申し込みはできますか?
A5:K会事務局までお問い合わせください。定員に余裕がある場合は、お電話でお申し込みを承ります。
イベント案内はこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
『円周率の秘密』
10月25日(土)14:00~16:00
講師:桝澤 海斗
イベント案内はこちらから
【よくあるご質問】
Q1:男女比はどれくらいですか?
A1:年によって異なりますが、2:1でやや男子生徒の方が多めです。
Q2:低学年ですが受講は可能ですか?
A2:学年で制限は設けておりません。分数・小数の計算、整数の性質(約数・倍数)図形の面積などについて理解されている方であれば学年を問わずご受講いただけます。
Q3:未就学児の弟・妹も一緒に連れていきたいのですが可能ですか。
A3:授業に参加することが難しい場合は控え室をご利用ください。教室の隣の部屋を保護者さまや小さなお子さまのための控え室としております。
Q4:当日必要なものはありますか?
A4:筆記用具をお持ちください。お持ちでない場合は貸し出しいたしますので、スタッフまでお声かけください。
Q5:申込期限を過ぎてしまいました。まだ申し込みはできますか?
A5:K会事務局までお問い合わせください。定員に余裕がある場合は、お電話でお申し込みを承ります。
イベント案内はこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
冬期講習のお申し込みについて
2025年10月14日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
来週、10/21(火)13:00から冬期講習の受付がはじまります!
設置講座は数学・英語・情報・物理・化学・生物・地理・天文学・言語学の全19講座!
詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/winter/kkai/
K会の冬期講習は、会員の方以外もお申込みいただけます。
毎年、受講いただいている生徒さんの半数以上がK会生以外の生徒さんです。
初めてK会の講座を受講するという生徒さんもたくさんいますので
「面白そう」 「学んでみたい」 「挑戦したい」
という気持ちがあれば、ぜひご受講ください!
言語学や天文学といった科学オリンピック講座をはじめ、方程式論や、化学の軌道論を扱う講座など、
学校では学ぶことのできない魅力的な講座をたくさんご用意してみなさんのお申し込みをお待ちしております。
講座は、下記お申し込みサイトにて10月21日(火)13:00よりお申し込みを承ります!
お申し込みはこちらから
【お問い合わせ】K会事務局
☎03-3813-4581 日・月除く 13:00~19:00
※日・月に加えて10月15日と12月30日~1月3日はお休み
来週、10/21(火)13:00から冬期講習の受付がはじまります!
設置講座は数学・英語・情報・物理・化学・生物・地理・天文学・言語学の全19講座!
詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/winter/kkai/
K会の冬期講習は、会員の方以外もお申込みいただけます。
毎年、受講いただいている生徒さんの半数以上がK会生以外の生徒さんです。
初めてK会の講座を受講するという生徒さんもたくさんいますので
「面白そう」 「学んでみたい」 「挑戦したい」
という気持ちがあれば、ぜひご受講ください!
言語学や天文学といった科学オリンピック講座をはじめ、方程式論や、化学の軌道論を扱う講座など、
学校では学ぶことのできない魅力的な講座をたくさんご用意してみなさんのお申し込みをお待ちしております。
講座は、下記お申し込みサイトにて10月21日(火)13:00よりお申し込みを承ります!
お申し込みはこちらから
【お問い合わせ】K会事務局
☎03-3813-4581 日・月除く 13:00~19:00
※日・月に加えて10月15日と12月30日~1月3日はお休み
━【「言語学をのぞいてみよう その42」(元K会英語科講師:野中大輔) 】━
2025年10月10日 更新
━【「言語学をのぞいてみよう その42」(元K会英語科講師:野中大輔) 】━
★このコラムでは、言語学を研究している筆者(元K会英語科講師)が、英語・言語学・外国語学習・比較文化などの話題をお伝えしていきます。★
「上下」「左右」「前後」「内外」のうち仲間外れは?
突然ですが、「上下」「左右」「前後」「内外」という二字熟語のうち、仲間外れはどれでしょうか? といっても、捻りのきいたなぞなぞを出題したいわけではなく、言語学の研究者である私だったら、どんなところに着目するのかをお話ししたいと思います。
まず、「上下」「左右」「前後」「内外」の構成を考えてみましょう。これらはいずれも反対の意味の漢字からなる熟語で、日本語にはこの種の熟語が多数あります(他には「大小」「貧富」「明暗」など)。「上下」「左右」「前後」「内外」はその中でも位置関係、空間関係を表すタイプであり、その点においてはよく似ています。
では、「上下」「左右」「前後」「内外」において、仲間外れがあるとすれば、どれでしょうか。私は日本語・英語の中でも特に動詞の研究を行っているので、ここでも動詞の観点から考えることにします。日本語では、名詞に分類される語に「〜する」を付けて動詞化することがよくあります(例:「料理する」「メールする」)。今回の4つの熟語に「~する」を付けてみると、「上下する」「左右する」「前後する」は自然な表現ですが、「内外する」は日本語としておかしく感じられることでしょう。中に入ったり外に出たりすることを「内外する」という表現で言い表してもよさそうですが、実際にはそのような言い方はしないわけですから、不思議なものです(一方で、「出入りする」という表現はありますね)。
今度は「上下する」「左右する」「前後する」の中で違いを探してみましょう。この3つの表現を使って例文を作ってみると、違いが見えてきます。「上下する」や「前後する」で例文を作るとすると、たとえば「値段が上下する」や「順番が前後する」などが思い浮かぶでしょう。それに対して、「左右する」の例文として自然なのは「この選択が運命を左右する」のような表現です。「上下する」と「前後する」は[Xが~する]の形で用いられるのが普通なのに対して、「左右する」は[XがYを~する]の形で使用されます。つまり、「上下する」「前後する」は自動詞(目的語を伴わない)であるのに対して、「左右する」は他動詞(目的語を伴う)なのです。「左右する」を「左に行ったり右に行ったりする」ことを表す自動詞として使うことがあってもよさそうに思えますが、試しに「風にあおられたボートが左右した」といった表現を作ってみれば、おかしいな、そんな言い方はしないなと感じられるでしょう。しかし、これは当たり前のことではなく、日本語を外国語として学習する人であれば、そのような表現を不自然だと感じずに使ってしまうかもしれません。なお、「左」と「右」を含む表現で自動詞として使うものとしては「右往左往する」があります(あわてふためくことを表す表現ですが)。
以上の内容をまとめると、「上下」「左右」「前後」「内外」のうち、動詞として使うかどうかという点では「内外」が仲間外れであり、動詞として使える3つのうち、自動詞として使うかどうかの点では、「左右(する)」が仲間外れということになります。同じような構成の表現なのに、こうした文法上の違いが見られるのは興味深いですね。
このような日本語の観察から、外国語学習についての教訓も得られます。まず、学習対象についての教訓です。日本語で「上下」「左右」「前後」「内外」のような表現を適切に使うためには、今回確認したような用法を身につけていなければなりません(そのような用法を身につけていないとおかしな表現を作ってしまう可能性があります)。同じく、外国語の表現を覚える際にも、その用法の範囲を知ることが重要です。たとえば「上下」に近い組み合わせとして、英語にはup and downという表現がありますが、単にupとdownを並べただけの表現だと思って終わらせるのではなく、どのような用法があるのかを意識的に学習することが必要です(up and downは副詞としてgo up and downのように用いられるほか、名詞としてups and downsの形にすると「(物事や気分の)浮き沈み、好不調」を表します)。
次に、「なぜ」という疑問との付き合い方について。おそらく、日本語において「内外する」とは言わない理由、「左右する」を他動詞としてしか使わない理由を考えても、納得のいく答えを見出すのは難しいと思われます。言語には〈たまたまそうなっている〉としか言いようのない側面も多々あります。それを受け入れるのも大事なことです。外国語を学んでいると様々な疑問が湧いてくるかと思いますが、「なぜ」については解消できないこともありますし、解消できなかったとしても必ずしも習得に支障はありません(たとえば、日本語を学習中の人は、「左右する」を他動詞としてしか使われない理由がわからなかったとしても、「この選択が運命を左右する」のような表現を学べるでしょう)。疑問を持つのは興味の表れですから、その気持ちは尊重しつつ、言語の実態を理解し、着実に身につけていく姿勢で外国語学習に向き合うことが大切です。
[補足]
「上下する」と「前後する」は「Xが~する]の形で用いられるのが普通であると述べましたが、「XがYを~する]の例も一部存在します。たとえば、「株価が一定の範囲を上下している」や「セミナーの出席者数が例年50人を前後しているので…」のように、Yに範囲や基準値などを表す名詞が現れる例などがあります。
★このコラムでは、言語学を研究している筆者(元K会英語科講師)が、英語・言語学・外国語学習・比較文化などの話題をお伝えしていきます。★
「上下」「左右」「前後」「内外」のうち仲間外れは?
突然ですが、「上下」「左右」「前後」「内外」という二字熟語のうち、仲間外れはどれでしょうか? といっても、捻りのきいたなぞなぞを出題したいわけではなく、言語学の研究者である私だったら、どんなところに着目するのかをお話ししたいと思います。
まず、「上下」「左右」「前後」「内外」の構成を考えてみましょう。これらはいずれも反対の意味の漢字からなる熟語で、日本語にはこの種の熟語が多数あります(他には「大小」「貧富」「明暗」など)。「上下」「左右」「前後」「内外」はその中でも位置関係、空間関係を表すタイプであり、その点においてはよく似ています。
では、「上下」「左右」「前後」「内外」において、仲間外れがあるとすれば、どれでしょうか。私は日本語・英語の中でも特に動詞の研究を行っているので、ここでも動詞の観点から考えることにします。日本語では、名詞に分類される語に「〜する」を付けて動詞化することがよくあります(例:「料理する」「メールする」)。今回の4つの熟語に「~する」を付けてみると、「上下する」「左右する」「前後する」は自然な表現ですが、「内外する」は日本語としておかしく感じられることでしょう。中に入ったり外に出たりすることを「内外する」という表現で言い表してもよさそうですが、実際にはそのような言い方はしないわけですから、不思議なものです(一方で、「出入りする」という表現はありますね)。
今度は「上下する」「左右する」「前後する」の中で違いを探してみましょう。この3つの表現を使って例文を作ってみると、違いが見えてきます。「上下する」や「前後する」で例文を作るとすると、たとえば「値段が上下する」や「順番が前後する」などが思い浮かぶでしょう。それに対して、「左右する」の例文として自然なのは「この選択が運命を左右する」のような表現です。「上下する」と「前後する」は[Xが~する]の形で用いられるのが普通なのに対して、「左右する」は[XがYを~する]の形で使用されます。つまり、「上下する」「前後する」は自動詞(目的語を伴わない)であるのに対して、「左右する」は他動詞(目的語を伴う)なのです。「左右する」を「左に行ったり右に行ったりする」ことを表す自動詞として使うことがあってもよさそうに思えますが、試しに「風にあおられたボートが左右した」といった表現を作ってみれば、おかしいな、そんな言い方はしないなと感じられるでしょう。しかし、これは当たり前のことではなく、日本語を外国語として学習する人であれば、そのような表現を不自然だと感じずに使ってしまうかもしれません。なお、「左」と「右」を含む表現で自動詞として使うものとしては「右往左往する」があります(あわてふためくことを表す表現ですが)。
以上の内容をまとめると、「上下」「左右」「前後」「内外」のうち、動詞として使うかどうかという点では「内外」が仲間外れであり、動詞として使える3つのうち、自動詞として使うかどうかの点では、「左右(する)」が仲間外れということになります。同じような構成の表現なのに、こうした文法上の違いが見られるのは興味深いですね。
このような日本語の観察から、外国語学習についての教訓も得られます。まず、学習対象についての教訓です。日本語で「上下」「左右」「前後」「内外」のような表現を適切に使うためには、今回確認したような用法を身につけていなければなりません(そのような用法を身につけていないとおかしな表現を作ってしまう可能性があります)。同じく、外国語の表現を覚える際にも、その用法の範囲を知ることが重要です。たとえば「上下」に近い組み合わせとして、英語にはup and downという表現がありますが、単にupとdownを並べただけの表現だと思って終わらせるのではなく、どのような用法があるのかを意識的に学習することが必要です(up and downは副詞としてgo up and downのように用いられるほか、名詞としてups and downsの形にすると「(物事や気分の)浮き沈み、好不調」を表します)。
次に、「なぜ」という疑問との付き合い方について。おそらく、日本語において「内外する」とは言わない理由、「左右する」を他動詞としてしか使わない理由を考えても、納得のいく答えを見出すのは難しいと思われます。言語には〈たまたまそうなっている〉としか言いようのない側面も多々あります。それを受け入れるのも大事なことです。外国語を学んでいると様々な疑問が湧いてくるかと思いますが、「なぜ」については解消できないこともありますし、解消できなかったとしても必ずしも習得に支障はありません(たとえば、日本語を学習中の人は、「左右する」を他動詞としてしか使われない理由がわからなかったとしても、「この選択が運命を左右する」のような表現を学べるでしょう)。疑問を持つのは興味の表れですから、その気持ちは尊重しつつ、言語の実態を理解し、着実に身につけていく姿勢で外国語学習に向き合うことが大切です。
[補足]
「上下する」と「前後する」は「Xが~する]の形で用いられるのが普通であると述べましたが、「XがYを~する]の例も一部存在します。たとえば、「株価が一定の範囲を上下している」や「セミナーの出席者数が例年50人を前後しているので…」のように、Yに範囲や基準値などを表す名詞が現れる例などがあります。
★小学生対象:数学イベントのお知らせ★
2025年10月5日 更新
小学生対象の数学イベントのお知らせです!
『円周率の秘密』
10月25日(土)14:00~16:00
講師:桝澤 海斗
イベント案内はこちらから
3.141592653589793238462643383279 ……
2025年5月「最も正確な円周率の値のギネス世界記録」が樹立されました。
その記録は、なんと小数点以下第300兆桁目まで求めたというものです。
きっと、この記録を人が手で計算したものだと思う方は少ないでしょう。もちろん、これはコンピュータを使って計算された記録です。
しかし、円周率の値を正確に求めようという試みは、古代から多くの人々が挑戦してきました。
現在わかっている最も古い円周率に関する記録は、1936年に発見された粘土板に記されたもので、紀元前2000頃の古代バビロニア時代(縄文時代の終わりごろ)のものです。
日本では江戸時代の数学者、松村茂清が1663年に小数点以下第7桁までを、関孝和が1681年に小数点以下第11桁までを正確に計算したものが古い記録として残っています。
ここで少し考えて見てください。コンピュータのない時代の数学者たちはどのようにして円周率を求めてきたのでしょうか。
この講座では、そんな電卓もコンピュータもない時代にタイムスリップして、当時実際に使われていた円周率を求める計算にチャレンジしていただきます。
自分の手で正確に計算することの、大変さや意外な難しさを通して、数学者の情熱と探究心を少しでも感じて頂けたら、大変嬉しく思います。
算数好きのお子さまはもちろん、保護者のみなさんにも楽しんでいただける内容です。
お子さまと一緒にぜひ気軽にご参加ください!
イベント案内はこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
『円周率の秘密』
10月25日(土)14:00~16:00
講師:桝澤 海斗
イベント案内はこちらから
3.141592653589793238462643383279 ……
2025年5月「最も正確な円周率の値のギネス世界記録」が樹立されました。
その記録は、なんと小数点以下第300兆桁目まで求めたというものです。
きっと、この記録を人が手で計算したものだと思う方は少ないでしょう。もちろん、これはコンピュータを使って計算された記録です。
しかし、円周率の値を正確に求めようという試みは、古代から多くの人々が挑戦してきました。
現在わかっている最も古い円周率に関する記録は、1936年に発見された粘土板に記されたもので、紀元前2000頃の古代バビロニア時代(縄文時代の終わりごろ)のものです。
日本では江戸時代の数学者、松村茂清が1663年に小数点以下第7桁までを、関孝和が1681年に小数点以下第11桁までを正確に計算したものが古い記録として残っています。
ここで少し考えて見てください。コンピュータのない時代の数学者たちはどのようにして円周率を求めてきたのでしょうか。
この講座では、そんな電卓もコンピュータもない時代にタイムスリップして、当時実際に使われていた円周率を求める計算にチャレンジしていただきます。
自分の手で正確に計算することの、大変さや意外な難しさを通して、数学者の情熱と探究心を少しでも感じて頂けたら、大変嬉しく思います。
算数好きのお子さまはもちろん、保護者のみなさんにも楽しんでいただける内容です。
お子さまと一緒にぜひ気軽にご参加ください!
イベント案内はこちらから
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから