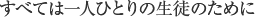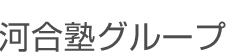スタッフからのお知らせK会本郷教室
34件の新着情報があります。 1-10件を表示
★夏期講習のお知らせ②★
2025年7月8日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
夏期講習の開始まで3週間を切りました!
近頃よく、「夏期講習の〇〇〇講座はまだ申し込めますか?」というお問合せをいただきます。
定期テストも終わり、夏の予定を考え始めた方も多いのではないでしょうか。現時点での申し込み状況は下表の通りになっております。
✕:締切 ▼:残り5名以下 △:残り10名以下 〇:残り10名以上
※数学オリンピックに学ぶ証明問題の考え方の映像受講については定員はございません
※講座の詳細はこちらから
初めてのご受講は不安かもしれませんが、講習初日に1階の受付カウンターで教室や施設のご案内をいたします。
また、忘れ物や先生への質問など、困ったことや自分一人では緊張することがあれば、
いつでもK会スタッフがサポートいたします!
「敷居が高い」「近寄りがたい」イメージがあるかもしれませんが、実はK会はとてもアットホームな場所です。
講師はもちろん、スタッフも優しく丁寧な方ばかりなので安心してくださいね。
夏期講習で皆さんとお会いできることを楽しみにしております♪
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
夏期講習の開始まで3週間を切りました!
近頃よく、「夏期講習の〇〇〇講座はまだ申し込めますか?」というお問合せをいただきます。
定期テストも終わり、夏の予定を考え始めた方も多いのではないでしょうか。現時点での申し込み状況は下表の通りになっております。
| ターム | 時限 | 講座名 | 空き状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 数 | ○ |
| 1 | 1 | Pythonではじめるプログラミング入門 | △ |
| 1 | 2 | 数学オリンピックに学ぶ証明問題の考え方 | ○ |
| 2 | 1 | 初等幾何 | ○ |
| 2 | 1 | 整数論 | ○ |
| 2 | 1 | 情報オリンピック予選問題に挑戦! | ○ |
| 2 | 2 | グラフ理論 | ○ |
| 2 | 2 | 英語で読む数学 | ○ |
| 2 | 2 | 物理数学 | ○ |
| 3 | 1 | サイバーセキュリテイ入門 | ▼ |
| 3 | 1 | 病理学入門 | ○ |
| 3 | 2 | 放射化学・核化学入門 | ○ |
| 3 | 2 | 地質学 | ○ |
| 3 | 2 | 古生物学 | ○ |
| 3 | 2 | 言語学オリンピックで入門する音韻論 | ○ |
| 4 | 1 | 座標幾何 | ○ |
| 4 | 1 | 形式言語理論と数理言語学 | ○ |
| 4 | 2 | 極限 | ○ |
| 4 | 2 | 楕円曲線上の有理点 | ○ |
| 4 | 2 | 地理オリンピック国内予選問題研究会2025 | △ |
※数学オリンピックに学ぶ証明問題の考え方の映像受講については定員はございません
※講座の詳細はこちらから
初めてのご受講は不安かもしれませんが、講習初日に1階の受付カウンターで教室や施設のご案内をいたします。
また、忘れ物や先生への質問など、困ったことや自分一人では緊張することがあれば、
いつでもK会スタッフがサポートいたします!
「敷居が高い」「近寄りがたい」イメージがあるかもしれませんが、実はK会はとてもアットホームな場所です。
講師はもちろん、スタッフも優しく丁寧な方ばかりなので安心してくださいね。
夏期講習で皆さんとお会いできることを楽しみにしております♪
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
※お申し込みはWebから
★夏期セミナーのご案内★
2025年7月4日 更新
本日は中高生とその保護者の方を対象とした夏期セミナーのお知らせです!
『数学を通して学ぶ音楽~音楽と数学の不思議な調和~』
7月26日(土)13:00~15:00
講演者:布施音人
講演案内はこちらから
数学と音楽の共通点は?
と問われたらみなさんは何か思いつくでしょうか。
論理的な数学と、感性に訴える音楽。全く違うように見える二つではありますが、人類は古くからこの2つに共通点を見出してきました。
例えば数学者として有名なピタゴラスもそのひとりです。ピタゴラス音律という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
ピタゴラス音律は音と音の周波数の比が1:2、2:3、3:4など特定の整数比のときに美しいハーモー二―になるというものです。
音楽に詳しい方はオクターブ、完全五度といった音程をイメージしてください。
ピタゴラスがこの音の性質に気づいたきっかけは、鍛冶屋(最近のみなさんは刀鍛冶といったら分かりやすいでしょうか。とあるアニメに刀を叩いて鍛えるシーンがありますよね。)の前を通りかかった時に響いていたハンマーの音だったそうです。
複数のハンマーの音が、美しく響くときとそうでないとき、その違いを調べたところハンマーの重さに違いがあることがわかりました。
そのハンマーとハンマーの重さの比が音の響きの美しさに関係しているというのが、ピタゴラス音律の発見のもとになったと言われています。
このピタゴラスように音の美しさを突き詰めて調べていくと、そこに数学的な法則が隠れていることがあります。
今回のセミナーではそんな音楽と数学のつながりを実際に楽器を使った演奏を交えながら分かりやすくご紹介していきます。
講師はK会数学科の元講師であり、ジャズピアニストとしても活躍されている布施音人さんです。
数学が好きな方も、音楽が好きな方も、ご家族やお友達をお誘いのうえお気軽にご参加下さい!
お申込・お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
『数学を通して学ぶ音楽~音楽と数学の不思議な調和~』
7月26日(土)13:00~15:00
講演者:布施音人
講演案内はこちらから
数学と音楽の共通点は?
と問われたらみなさんは何か思いつくでしょうか。
論理的な数学と、感性に訴える音楽。全く違うように見える二つではありますが、人類は古くからこの2つに共通点を見出してきました。
例えば数学者として有名なピタゴラスもそのひとりです。ピタゴラス音律という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
ピタゴラス音律は音と音の周波数の比が1:2、2:3、3:4など特定の整数比のときに美しいハーモー二―になるというものです。
音楽に詳しい方はオクターブ、完全五度といった音程をイメージしてください。
ピタゴラスがこの音の性質に気づいたきっかけは、鍛冶屋(最近のみなさんは刀鍛冶といったら分かりやすいでしょうか。とあるアニメに刀を叩いて鍛えるシーンがありますよね。)の前を通りかかった時に響いていたハンマーの音だったそうです。
複数のハンマーの音が、美しく響くときとそうでないとき、その違いを調べたところハンマーの重さに違いがあることがわかりました。
そのハンマーとハンマーの重さの比が音の響きの美しさに関係しているというのが、ピタゴラス音律の発見のもとになったと言われています。
このピタゴラスように音の美しさを突き詰めて調べていくと、そこに数学的な法則が隠れていることがあります。
今回のセミナーではそんな音楽と数学のつながりを実際に楽器を使った演奏を交えながら分かりやすくご紹介していきます。
講師はK会数学科の元講師であり、ジャズピアニストとしても活躍されている布施音人さんです。
数学が好きな方も、音楽が好きな方も、ご家族やお友達をお誘いのうえお気軽にご参加下さい!
お申込・お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
★数学オリンピック講座のご案内★
2025年6月18日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
夏期講習の申し込みが始まり一週間が経ちました。
受付初日から、たくさんの方にお申込をいただき大変嬉しく思っております!
現時点で締切講座はございません。各講座の詳細は下記HPよりご覧いただけます。
https://www.kawai-juku.ac.jp/summer/kkai/
さて、K会と言えば、「数学オリンピック」を真っ先に思い浮かべてくださる方も多いのではないでしょうか。
今年の1月に行われた第35回日本数学オリンピックの予選通過者は207名
そのうちK会生および、K会の講習等を受けてくださった方は17名
予選通過者の8%がK会の講座を受講しています!
さらに、本選の成績優秀者でみてみると20名中7名、つまり3割以上の方がK会の利用者です!!
国際数学オリンピックでメダルを獲得した講師から直接指導を受けられるのはK会ならでは。
「今まで問題を解くことに重点を置いてきて、必要な知識や取り組み方を意識したことがなかったので勉強になりました」(高1・桜蔭)
「問題に対してのアプローチがぐっと増えました。視点を変えて見る力が付いたと思います。」(高1・開成)
次こそは!と予選突破&代表入りを目指す皆さん!!
K会で数オリ講座を受講してみませんか?
対面授業:7月29日(火)~8月1日(金)17:30-20:40
録画配信:8月12日(火)~9月16日(火)
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
★講習のお申し込みはこちらから
夏期講習の申し込みが始まり一週間が経ちました。
受付初日から、たくさんの方にお申込をいただき大変嬉しく思っております!
現時点で締切講座はございません。各講座の詳細は下記HPよりご覧いただけます。
https://www.kawai-juku.ac.jp/summer/kkai/
さて、K会と言えば、「数学オリンピック」を真っ先に思い浮かべてくださる方も多いのではないでしょうか。
今年の1月に行われた第35回日本数学オリンピックの予選通過者は207名
そのうちK会生および、K会の講習等を受けてくださった方は17名
予選通過者の8%がK会の講座を受講しています!
さらに、本選の成績優秀者でみてみると20名中7名、つまり3割以上の方がK会の利用者です!!
国際数学オリンピックでメダルを獲得した講師から直接指導を受けられるのはK会ならでは。
「今まで問題を解くことに重点を置いてきて、必要な知識や取り組み方を意識したことがなかったので勉強になりました」(高1・桜蔭)
「問題に対してのアプローチがぐっと増えました。視点を変えて見る力が付いたと思います。」(高1・開成)
次こそは!と予選突破&代表入りを目指す皆さん!!
K会で数オリ講座を受講してみませんか?
対面授業:7月29日(火)~8月1日(金)17:30-20:40
録画配信:8月12日(火)~9月16日(火)
お問合せ
K会事務局 ☎03-3813-4581
受付時間 火~土曜日(13:00-19:00)
★講習のお申し込みはこちらから
★夏期講習の申込が始まりました★
2025年6月10日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
本日6/10(火)13:00から夏期講習の受付がはじまります!
設置講座は数学・英語・情報・物理・化学・生物・地理・地学・言語学の全20講座!
詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/summer/kkai/
K会の夏期講習は、会員の方以外もお申込みいただけます。
毎年、受講いただいている生徒さんの半数以上がK会生以外の生徒さんです。
初めてK会の講座を受講するという生徒さんもたくさんいますので
「面白そう」 「学んでみたい」 「挑戦したい」
という気持ちがあれば、ぜひご受講ください!
科学オリンピック講座をはじめ、病理学や、地質学、古生物学など、
学校では学ぶことのできない魅力的な講座をたくさんご用意してみなさんのお申し込みをお待ちしております!!
【お問い合わせ】K会事務局
☎03-3813-4581 日・月除く 13:00~19:00
本日6/10(火)13:00から夏期講習の受付がはじまります!
設置講座は数学・英語・情報・物理・化学・生物・地理・地学・言語学の全20講座!
詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/summer/kkai/
K会の夏期講習は、会員の方以外もお申込みいただけます。
毎年、受講いただいている生徒さんの半数以上がK会生以外の生徒さんです。
初めてK会の講座を受講するという生徒さんもたくさんいますので
「面白そう」 「学んでみたい」 「挑戦したい」
という気持ちがあれば、ぜひご受講ください!
科学オリンピック講座をはじめ、病理学や、地質学、古生物学など、
学校では学ぶことのできない魅力的な講座をたくさんご用意してみなさんのお申し込みをお待ちしております!!
【お問い合わせ】K会事務局
☎03-3813-4581 日・月除く 13:00~19:00
━【「音楽から見る数学13」(元K会生・元K会数学科講師:布施音人) 】━
2025年6月8日 更新
━【「音楽から見る数学13」(元K会生・元K会数学科講師:布施音人) 】━
★このコラムでは、数学と音楽の両方に魅せられてきた筆者が、数学と音楽の共通点を考える中で見えてくる数学の魅力について、筆者なりの言葉でお伝えしていきます★
― 楽式と繰り返し構造 ―
こんにちは。元K会数学科講師の布施音人です。
今回も数学とは直接関わらない音楽の話をしたいと思います。
みなさんは「ロンド形式」「ソナタ形式」といった言葉を聞いたことがありますか?これらは楽曲の形式(=楽式)を表す言葉で、西洋クラシック音楽の多くの楽曲が(作曲者自身が意識していたか否かはさておき)これらの形式に沿って書かれています。今日はこれらをはじめとした楽曲の形式について述べたいと思います。
ところで、楽曲の形式とはなんでしょうか?あらためて言語化するのは難しいですが、楽曲を「ひとかたまり」に見える部分に分解したときの、それらの関係、と言い換えられるかもしれません。
たとえば「きらきら星」で言えば、「きらきらひかる おそらのほしよ」まででひとかたまり、「まばたきしては みんなをみてる」が次のひとかたまり、「きらきらひかる おそらのほしよ」が最後のひとかたまりと見なせます。このとき、1個目と3個目は同じメロディで、2個目だけが他のメロディになっています。このような形式は「ABA」のように書かれることがあります。一般に3つの部分に分けて捉えられる楽曲の形式を「三部形式」と呼ぶことがありますが、これはその一種と言えます。
また、現代の日本のポップスの楽曲は「Aメロ→Bメロ→サビ→間奏→Aメロ→Bメロ→サビ→Cメロ→サビ→終結部」といった形式を取ることがありますが、これも楽曲の形式の典型例です。
これらの形式は入れ子構造になる場合も多々あります。たとえば、先ほど「ABA」のタイプの三部形式について触れましたが、そのAやB自体が更に細かく見ると同じタイプの三部形式となっているような楽曲がクラシックには多数存在します。「A」を分解すると「aba」、「B」は「cdc」のようになっていて、「aba cdc aba」のような構造をしている、ということです(複合三部形式と呼ばれたりします)。
さて、ではなぜ人間は楽曲をこういった形式に沿って作ってきたのでしょうか?明確な答えが出るものではないと思いますが、人間が楽曲を知覚するときの仕組みに深く関わっていると私は考えています。
例として「AABA」という形式の楽曲について考えましょう。20世紀アメリカのポピュラー音楽でも大変よく見られた形式で、有名な「Over The Rainbow」などもこの形式です。この形式の楽曲を聴いた人の心の動きは次のようになると思います(あくまで一例です)。まず最初のAでは、どんな曲が始まるのだろう、と注意を払いながら音楽に耳を傾けます。そして次のAは最初のAの繰り返しですから、少しリラックスして旋律の美しさを味わったり、歌詞の意味を考えたりします。そして次はAの繰り返しではなく全く別のBが訪れ、一種の驚きが生まれます。この驚きが脳へのスパイスとなり、気分が高まったり、感動を味わったりします(この部分をサビと呼んだりします)。そして最後に再びAが訪れ、家へ帰ったような安心感と、一つの旅をしてきたような充足感を味わいます。「起承転結」と言い換えれば早いかもしれません。
音楽は常に時間と共にあり、立ち止まったり巻き戻ったりすることなく流れて行ってしまうものですから、人が音楽を聴くプロセスは、フレーズなど楽曲の断片を一時的に記憶し、それと照らし合わせながら続きを聴いていくことだと言えます。そのため、人は無意識のうちに、楽曲の中に潜む繰り返し構造と、そこからのズレ(全く違うBパートが現れたり、同じAパートでも少しメロディに変化があったり、など)に着目しているのだと思います。
なお、楽曲の形式という概念は、曲全体をいくつかのブロックに分ける話にとどまりません。たとえば「かえるのうた」のような輪唱は、ひとかたまりに見えるもの(メロディー)をタイミングをずらして同時に演奏するというものですが、これもカノン形式、カノン様式と呼ばれる一つの形式です。
世の中には多数の楽曲がありますが、その形式が人の心にどういった動きをもたらすのかにも着目しながら聴いてみると、新たな発見があるかもしれません。
★このコラムでは、数学と音楽の両方に魅せられてきた筆者が、数学と音楽の共通点を考える中で見えてくる数学の魅力について、筆者なりの言葉でお伝えしていきます★
― 楽式と繰り返し構造 ―
こんにちは。元K会数学科講師の布施音人です。
今回も数学とは直接関わらない音楽の話をしたいと思います。
みなさんは「ロンド形式」「ソナタ形式」といった言葉を聞いたことがありますか?これらは楽曲の形式(=楽式)を表す言葉で、西洋クラシック音楽の多くの楽曲が(作曲者自身が意識していたか否かはさておき)これらの形式に沿って書かれています。今日はこれらをはじめとした楽曲の形式について述べたいと思います。
ところで、楽曲の形式とはなんでしょうか?あらためて言語化するのは難しいですが、楽曲を「ひとかたまり」に見える部分に分解したときの、それらの関係、と言い換えられるかもしれません。
たとえば「きらきら星」で言えば、「きらきらひかる おそらのほしよ」まででひとかたまり、「まばたきしては みんなをみてる」が次のひとかたまり、「きらきらひかる おそらのほしよ」が最後のひとかたまりと見なせます。このとき、1個目と3個目は同じメロディで、2個目だけが他のメロディになっています。このような形式は「ABA」のように書かれることがあります。一般に3つの部分に分けて捉えられる楽曲の形式を「三部形式」と呼ぶことがありますが、これはその一種と言えます。
また、現代の日本のポップスの楽曲は「Aメロ→Bメロ→サビ→間奏→Aメロ→Bメロ→サビ→Cメロ→サビ→終結部」といった形式を取ることがありますが、これも楽曲の形式の典型例です。
これらの形式は入れ子構造になる場合も多々あります。たとえば、先ほど「ABA」のタイプの三部形式について触れましたが、そのAやB自体が更に細かく見ると同じタイプの三部形式となっているような楽曲がクラシックには多数存在します。「A」を分解すると「aba」、「B」は「cdc」のようになっていて、「aba cdc aba」のような構造をしている、ということです(複合三部形式と呼ばれたりします)。
さて、ではなぜ人間は楽曲をこういった形式に沿って作ってきたのでしょうか?明確な答えが出るものではないと思いますが、人間が楽曲を知覚するときの仕組みに深く関わっていると私は考えています。
例として「AABA」という形式の楽曲について考えましょう。20世紀アメリカのポピュラー音楽でも大変よく見られた形式で、有名な「Over The Rainbow」などもこの形式です。この形式の楽曲を聴いた人の心の動きは次のようになると思います(あくまで一例です)。まず最初のAでは、どんな曲が始まるのだろう、と注意を払いながら音楽に耳を傾けます。そして次のAは最初のAの繰り返しですから、少しリラックスして旋律の美しさを味わったり、歌詞の意味を考えたりします。そして次はAの繰り返しではなく全く別のBが訪れ、一種の驚きが生まれます。この驚きが脳へのスパイスとなり、気分が高まったり、感動を味わったりします(この部分をサビと呼んだりします)。そして最後に再びAが訪れ、家へ帰ったような安心感と、一つの旅をしてきたような充足感を味わいます。「起承転結」と言い換えれば早いかもしれません。
音楽は常に時間と共にあり、立ち止まったり巻き戻ったりすることなく流れて行ってしまうものですから、人が音楽を聴くプロセスは、フレーズなど楽曲の断片を一時的に記憶し、それと照らし合わせながら続きを聴いていくことだと言えます。そのため、人は無意識のうちに、楽曲の中に潜む繰り返し構造と、そこからのズレ(全く違うBパートが現れたり、同じAパートでも少しメロディに変化があったり、など)に着目しているのだと思います。
なお、楽曲の形式という概念は、曲全体をいくつかのブロックに分ける話にとどまりません。たとえば「かえるのうた」のような輪唱は、ひとかたまりに見えるもの(メロディー)をタイミングをずらして同時に演奏するというものですが、これもカノン形式、カノン様式と呼ばれる一つの形式です。
世の中には多数の楽曲がありますが、その形式が人の心にどういった動きをもたらすのかにも着目しながら聴いてみると、新たな発見があるかもしれません。
━【「現代数学の視座と眺望6」(元K会数学科講師:立原礼也) 】━
2025年5月9日 更新
━【現代数学の視座と眺望№6(K会元数学科講師:立原礼也) 】━
★「現代数学」、つまり大雑把には「大学の数学科レベルの数学」は、中高で習う数学と地続きに繋がっていながらも、様々な面で、全く新しい考え方に基づくものでもあります。筆者が数学を専攻することに決めたのも、この新しくも自然な考え方の数々に魅了されてのことでした。このコラムでは、現代数学におけるものの見方=「視座」、そしてそれによるものの見え方=「眺望」の解説を通じ、現代数学の魅力の一端をお伝えしていきます★
数学の抽象化と難しさ
読者の皆さん、こんにちは。
K会数学科元講師の立原礼也と申します。
第6回目となる今回から次回の第7回にかけては、数学という学問の重要な側面の1つである「抽象化」を話題にしてみたいと思います。大げさな話に見えるかもしれませんが、これは中学校で習う「方程式の文章題」という初等的な例を通じても観察することができるものです。その意味では、この話題は「現代数学」とは限らない(中高レベルも含めた)「数学」にも通用するものであり、連載の趣旨から外れてしまうのかもしれません。一方、筆者が今回の内容のようなことを本格的に考え出したきっかけは、もう10年近く前になりますが、現代数学の勉強を始めたころの苦労の経験であり、それゆえに筆者としては今回から次回にかけての内容が現代数学を学ぼうとする方の参考になることを願い、期待しているものです。
それでは、次のような「方程式の文章題」に対する、「算数的(?)解法」と「数学的(?)解法」の比較から、議論を始めましょう。なお、誤解を防ぐために先に述べておきますと、ここで言いたいのは「どちらの方が良い解法だ」といった優劣比較ではありません。(ある特定の観点からの優劣比較は後に出てきますが、それは記事の主旨ではありません。)また、今回たまたま例示がこのようなものになっただけであって、筆者は「算数と数学の違い」のようなことを論じたいわけでもありません。
問題
ノート1冊は鉛筆1本より40円高く、ノート1冊と鉛筆1本の合計金額は100円であるとする。鉛筆は1本いくらか。
解法1(算数的?)
100-40=60 (鉛筆2本の値段)
60÷2=30 (鉛筆1本の値段)
よって、「30円」
解法2(数学的?)
鉛筆1本の値段をx円とおくと、条件は
x+(x+40)=100
これを解くとx=30
よって、「30円」
この2つの解法の共通点と相違点を観察しましょう。まず共通点ですが、「行われている実質的な計算の内容は一緒である」ことが挙げられると思います。実際、解法2において方程式を解くプロセスを書き下すと、
2x=100-40=60
x=60÷2=30
のようになり、解法1において行われる計算の内容と一緒になります。この意味では解法1と解法2は「全く同じ解法だ」と認識する人がいてもおかしくはないでしょう。にもかかわらず筆者は、解法1と解法2には明確な相違点があると考えているのです。
では、筆者の考える2つの解法の相違点を説明しましょう。
解法1においては、途中の計算に対して、考察下の問題設定の観点からの「物理的な・現実的な・実体的な意味」が付与されています。つまり例えば、途中で行った100-40=60という計算は、ただの抽象的な数の計算ではなくて、「この数値が鉛筆2本分の値段を表している」という認識、意味付けの下で行われているということです。対照的に、解法2においては、途中の計算2x=100-40=60は抽象的な数の計算です。もちろん、「我々は鉛筆1本の値段をx円としていたのであった」ということを思い出せば、その情報によって、解法2におけるこの式にも「物理的な・現実的な・実体的な意味」を付与することは可能です。しかし、中学校1年生で習う「方程式の考え方を用いて文章題を解く」方法の重要な点はむしろ、途中の計算に意味を付与しないこと、途中で「我々は鉛筆1本の値段をx円としていたのであった」などと思い出したりしないこと、にあるのではないでしょうか。ですから、この「途中の計算に意味を付与するかどうか」という点は、解法1と解法2の大きな違いだと言えると思います。今回は易しめの問題を選んでみましたが、どんな文章題でも、「算数的(?)解法」と「数学的(?)解法」の間には、同様の違いが見出されるはずです。
しつこいようですが、解法2で何が起きているのか、もう一度説明させてください。「ノート1冊は鉛筆1本より40円高く、ノート1冊と鉛筆1本の合計金額は100円であるとする。」という問題文は、物理的な・現実的な・実体的な状況の説明を与えるものであり、つまりこの問題文は「現実の世界」に属しています。我々はそれを「鉛筆1本の値段をx円とおく」ことでx+(x+40)=100という数式に翻訳・変換します。このx+(x+40)=100という方程式は「現実の世界」ではなく、抽象的な、「数式の世界」に住まうものです。解法2では、ひとたびこの「数式の世界」にいる(そして「現実の世界」にはいない)x+(x+40)=100を得たら、一度も「現実の世界」との関連に立ち返ることなく、純粋に「数式の世界」で完結した処理によって、x=30を導きます。そして、ここまできて、最後の最後に、初めて「鉛筆1本の値段をx円とおく」というルールを思い出し、「鉛筆1本は30円」と結論するのです。まとめましょう。「現実の世界」から「数式の世界」にひとたび移ったら、その「数式の世界」で完結する(「現実の世界」との結びつきは考えない)処理を行い、一番最後に得られた結果を再度「現実の世界」に翻訳する。これが解法2の、ひいては中学校で習う「文章題の方程式による解法」全般に見られる、論理的な構造です。
こう見ると、解法1と解法2の相違点も明確ではないでしょうか。解法1において、100-40=60といった計算そのものは「数式の世界」に属していますが、我々はそれを「現実の世界」と切り離してはいません。100-40が「現実の世界」における何に対応しているのかを、明確に意識しています。そして、その意識があるからこそ、続く60÷2=30という計算にも意味が付与され、30円が答えであることが直ちにわかるのです。ここでは常に「現実の世界」と「数式の世界」が結びついています。この結びつき、あるいは結びつけ続けたまま処理を行うことを、筆者は個人的に「同期化」と呼んでいます。解法1においては、「現実の世界」での理解と「数式の世界」での理解が常に同期化され、同時並行で進んでいるのです。解法2にはこうした同期化が見られません。
相違点がわかったところで、議論をさらに進めましょう。最初に述べた通り、解法1と解法2はどちらが優れているというわけではなく、それぞれの良いところがあります。まず、解法1の良いところは、同義反復的ですが、考察下の物理的な・現実的な・実体的な状況に対して理解が深められるところです。なにしろ、計算過程にも常に意味が付与されているのですから、当然、より多くのことを網羅的に理解でき、手持ちの情報が多くなります。また、途中経過の全ての部分に意味がつくということは、途中の議論の全てに素朴に納得感をもって、安心して答えを出せるということでもあると思います。
解法2の良いところとして、解法1と違って途中経過で保持しておかなければならない情報が少ないぶん、ひとたび抽象的な計算(=例えば、方程式の同値変形)の仕組みさえ理解してしまえば、思考負荷が非常に小さくなる、ということが挙げられると思います。また、途中経過に意味を付与する必要がないため、計算の自由度が大幅に上がります。例えば-2x=-60等といった負の数の式が出てくると、これに「物理的な・現実的な・実体的な意味」を端的にわかりやすく与えるのは少し大変になりますが、そうした困難性は方程式の計算の上では全く支障にならないわけです。更に、こうした自由度の向上が、解決可能な問題の範囲の拡張に本質的に寄与する場合もあります。実際、3次以上の方程式(が出てくるような問題)になると、最終的な解には「物理的な・現実的な・実体的な意味」が付くような状況であったとしても、解法の途中では虚数(当コラム第1回および第2回を参照)まで使うはめになる、といった場合もあるのです。(というより。歴史的にはこれが虚数を導入する1つの契機になったようです。詳細を知りたい方は数学史の本をご覧ください。)
筆者は先に「2つの解法の優劣比較をしたいわけではない」と述べました。一方、しかしながら、何か特定の、限定的な観点に立てば、その観点から優劣がつくのも当たり前なことです。そして、上に見てきた通り、「計算の自由度」やそれに伴う「汎用性」といった観点からは、解法2は解法1を上回っていると考えられます。こうした抽象化(=今回の例で言えば、様々な問題解決に統一的な視座を与える「方程式を解く」という仕組み)による汎用性の向上は、数学の発展の1つの典型的な方向性であり、その意味では解法2は解法1より進んだ考え方だとみることもできます。
抽象化は「方程式の文章題」の例だけで見ても素晴らしいものだとわかりますし、また前回記事の代数的整数論の話題も、抽象化の威力を示す例となっています。一方、当たり前な話ですが、このような、より抽象化された、進んだ数学は、それだけ習得や納得のハードルが上がるという側面もあります。何しろ、抽象化というのは、まさに「それまで依拠していた具体的な文脈から離脱してしまう」ということなのですから、物事をどういう風に考えたらいいのか、見失いやすくなります。例えば「方程式の文章題」の例ですと、解法2において重要な役割を果たした方程式の同値変形の仕組みは、「現実の世界」とは切り離されて純粋に「数式の世界」に属するものであり、これについて納得して理解することは中学数学の最初の関門となるでしょう。また、そのようにして具体的な文脈から離脱した抽象的手法の適用によって、最終的に具体的な成果が得られたとしても、「狐につままれた」ような感じで納得しづらい、と思う人もいるのではないでしょうか。方程式を解いて「現実の世界」の答えが得られること、素数を平方和で表す方法の存在・非存在が複素数を使ってわかること(前回記事参照)、改めて考えてみると何だか魔法のようです。
筆者の場合、幸運にも中高数学の勉強の段階ではこのような抽象性について困難を感じずに済みましたが、大学レベル(現代数学)の勉強を始めた後は、多くの苦労を経験しました。現代数学ですと、一口に抽象化とは言っても最初から現実世界とは切り離された純粋数学の枠組内でのそれが多いので、その意味では「方程式の文章題」の例と様子が違っているのですが、それでも学習上の困難の在り方自体は上述したものと同様です。では、このような抽象性に由来する習得・納得の困難に立ち向かうためには、我々はどうすればよいのでしょうか?これは決まった答えのない難しい問題ですが、筆者なりに考えていることがいくつかあります。そこで次回は筆者の個人的な経験に基づいて、抽象的な数学の学習に関するいくつかのコメントを述べてみたいと思います。
**********
(意欲ある読者に向けた、答えのない演習問題)
1.様々な「方程式の文章題」について、「解法1」のような解き方と、「解法2」のような解き方を与え、それらを比較した考察を与えてみてください。
2.次回は、抽象的な数学を学ぶ上での困難にどのように立ち向かうか、ということを話題にしたいと思います。そのトイモデルとして、解法2に出てくるような方程式の同値変形の仕組みがわからず困っている人が、どのように学習を進めたら良さそうか、考えてみてください。(もちろん、どのような方法が最適かは人によると思いますが、その方法の候補を考えてみてください、ということです。)例えば、「解き方のパターンを、理屈は気にせず丸暗記する」という方法には、どのようなメリットとデメリットがあるでしょうか?また、こういった考察から、抽象的な数学の学習全般への示唆は何か得られるでしょうか?
★「現代数学」、つまり大雑把には「大学の数学科レベルの数学」は、中高で習う数学と地続きに繋がっていながらも、様々な面で、全く新しい考え方に基づくものでもあります。筆者が数学を専攻することに決めたのも、この新しくも自然な考え方の数々に魅了されてのことでした。このコラムでは、現代数学におけるものの見方=「視座」、そしてそれによるものの見え方=「眺望」の解説を通じ、現代数学の魅力の一端をお伝えしていきます★
数学の抽象化と難しさ
読者の皆さん、こんにちは。
K会数学科元講師の立原礼也と申します。
第6回目となる今回から次回の第7回にかけては、数学という学問の重要な側面の1つである「抽象化」を話題にしてみたいと思います。大げさな話に見えるかもしれませんが、これは中学校で習う「方程式の文章題」という初等的な例を通じても観察することができるものです。その意味では、この話題は「現代数学」とは限らない(中高レベルも含めた)「数学」にも通用するものであり、連載の趣旨から外れてしまうのかもしれません。一方、筆者が今回の内容のようなことを本格的に考え出したきっかけは、もう10年近く前になりますが、現代数学の勉強を始めたころの苦労の経験であり、それゆえに筆者としては今回から次回にかけての内容が現代数学を学ぼうとする方の参考になることを願い、期待しているものです。
それでは、次のような「方程式の文章題」に対する、「算数的(?)解法」と「数学的(?)解法」の比較から、議論を始めましょう。なお、誤解を防ぐために先に述べておきますと、ここで言いたいのは「どちらの方が良い解法だ」といった優劣比較ではありません。(ある特定の観点からの優劣比較は後に出てきますが、それは記事の主旨ではありません。)また、今回たまたま例示がこのようなものになっただけであって、筆者は「算数と数学の違い」のようなことを論じたいわけでもありません。
問題
ノート1冊は鉛筆1本より40円高く、ノート1冊と鉛筆1本の合計金額は100円であるとする。鉛筆は1本いくらか。
解法1(算数的?)
100-40=60 (鉛筆2本の値段)
60÷2=30 (鉛筆1本の値段)
よって、「30円」
解法2(数学的?)
鉛筆1本の値段をx円とおくと、条件は
x+(x+40)=100
これを解くとx=30
よって、「30円」
この2つの解法の共通点と相違点を観察しましょう。まず共通点ですが、「行われている実質的な計算の内容は一緒である」ことが挙げられると思います。実際、解法2において方程式を解くプロセスを書き下すと、
2x=100-40=60
x=60÷2=30
のようになり、解法1において行われる計算の内容と一緒になります。この意味では解法1と解法2は「全く同じ解法だ」と認識する人がいてもおかしくはないでしょう。にもかかわらず筆者は、解法1と解法2には明確な相違点があると考えているのです。
では、筆者の考える2つの解法の相違点を説明しましょう。
解法1においては、途中の計算に対して、考察下の問題設定の観点からの「物理的な・現実的な・実体的な意味」が付与されています。つまり例えば、途中で行った100-40=60という計算は、ただの抽象的な数の計算ではなくて、「この数値が鉛筆2本分の値段を表している」という認識、意味付けの下で行われているということです。対照的に、解法2においては、途中の計算2x=100-40=60は抽象的な数の計算です。もちろん、「我々は鉛筆1本の値段をx円としていたのであった」ということを思い出せば、その情報によって、解法2におけるこの式にも「物理的な・現実的な・実体的な意味」を付与することは可能です。しかし、中学校1年生で習う「方程式の考え方を用いて文章題を解く」方法の重要な点はむしろ、途中の計算に意味を付与しないこと、途中で「我々は鉛筆1本の値段をx円としていたのであった」などと思い出したりしないこと、にあるのではないでしょうか。ですから、この「途中の計算に意味を付与するかどうか」という点は、解法1と解法2の大きな違いだと言えると思います。今回は易しめの問題を選んでみましたが、どんな文章題でも、「算数的(?)解法」と「数学的(?)解法」の間には、同様の違いが見出されるはずです。
しつこいようですが、解法2で何が起きているのか、もう一度説明させてください。「ノート1冊は鉛筆1本より40円高く、ノート1冊と鉛筆1本の合計金額は100円であるとする。」という問題文は、物理的な・現実的な・実体的な状況の説明を与えるものであり、つまりこの問題文は「現実の世界」に属しています。我々はそれを「鉛筆1本の値段をx円とおく」ことでx+(x+40)=100という数式に翻訳・変換します。このx+(x+40)=100という方程式は「現実の世界」ではなく、抽象的な、「数式の世界」に住まうものです。解法2では、ひとたびこの「数式の世界」にいる(そして「現実の世界」にはいない)x+(x+40)=100を得たら、一度も「現実の世界」との関連に立ち返ることなく、純粋に「数式の世界」で完結した処理によって、x=30を導きます。そして、ここまできて、最後の最後に、初めて「鉛筆1本の値段をx円とおく」というルールを思い出し、「鉛筆1本は30円」と結論するのです。まとめましょう。「現実の世界」から「数式の世界」にひとたび移ったら、その「数式の世界」で完結する(「現実の世界」との結びつきは考えない)処理を行い、一番最後に得られた結果を再度「現実の世界」に翻訳する。これが解法2の、ひいては中学校で習う「文章題の方程式による解法」全般に見られる、論理的な構造です。
こう見ると、解法1と解法2の相違点も明確ではないでしょうか。解法1において、100-40=60といった計算そのものは「数式の世界」に属していますが、我々はそれを「現実の世界」と切り離してはいません。100-40が「現実の世界」における何に対応しているのかを、明確に意識しています。そして、その意識があるからこそ、続く60÷2=30という計算にも意味が付与され、30円が答えであることが直ちにわかるのです。ここでは常に「現実の世界」と「数式の世界」が結びついています。この結びつき、あるいは結びつけ続けたまま処理を行うことを、筆者は個人的に「同期化」と呼んでいます。解法1においては、「現実の世界」での理解と「数式の世界」での理解が常に同期化され、同時並行で進んでいるのです。解法2にはこうした同期化が見られません。
相違点がわかったところで、議論をさらに進めましょう。最初に述べた通り、解法1と解法2はどちらが優れているというわけではなく、それぞれの良いところがあります。まず、解法1の良いところは、同義反復的ですが、考察下の物理的な・現実的な・実体的な状況に対して理解が深められるところです。なにしろ、計算過程にも常に意味が付与されているのですから、当然、より多くのことを網羅的に理解でき、手持ちの情報が多くなります。また、途中経過の全ての部分に意味がつくということは、途中の議論の全てに素朴に納得感をもって、安心して答えを出せるということでもあると思います。
解法2の良いところとして、解法1と違って途中経過で保持しておかなければならない情報が少ないぶん、ひとたび抽象的な計算(=例えば、方程式の同値変形)の仕組みさえ理解してしまえば、思考負荷が非常に小さくなる、ということが挙げられると思います。また、途中経過に意味を付与する必要がないため、計算の自由度が大幅に上がります。例えば-2x=-60等といった負の数の式が出てくると、これに「物理的な・現実的な・実体的な意味」を端的にわかりやすく与えるのは少し大変になりますが、そうした困難性は方程式の計算の上では全く支障にならないわけです。更に、こうした自由度の向上が、解決可能な問題の範囲の拡張に本質的に寄与する場合もあります。実際、3次以上の方程式(が出てくるような問題)になると、最終的な解には「物理的な・現実的な・実体的な意味」が付くような状況であったとしても、解法の途中では虚数(当コラム第1回および第2回を参照)まで使うはめになる、といった場合もあるのです。(というより。歴史的にはこれが虚数を導入する1つの契機になったようです。詳細を知りたい方は数学史の本をご覧ください。)
筆者は先に「2つの解法の優劣比較をしたいわけではない」と述べました。一方、しかしながら、何か特定の、限定的な観点に立てば、その観点から優劣がつくのも当たり前なことです。そして、上に見てきた通り、「計算の自由度」やそれに伴う「汎用性」といった観点からは、解法2は解法1を上回っていると考えられます。こうした抽象化(=今回の例で言えば、様々な問題解決に統一的な視座を与える「方程式を解く」という仕組み)による汎用性の向上は、数学の発展の1つの典型的な方向性であり、その意味では解法2は解法1より進んだ考え方だとみることもできます。
抽象化は「方程式の文章題」の例だけで見ても素晴らしいものだとわかりますし、また前回記事の代数的整数論の話題も、抽象化の威力を示す例となっています。一方、当たり前な話ですが、このような、より抽象化された、進んだ数学は、それだけ習得や納得のハードルが上がるという側面もあります。何しろ、抽象化というのは、まさに「それまで依拠していた具体的な文脈から離脱してしまう」ということなのですから、物事をどういう風に考えたらいいのか、見失いやすくなります。例えば「方程式の文章題」の例ですと、解法2において重要な役割を果たした方程式の同値変形の仕組みは、「現実の世界」とは切り離されて純粋に「数式の世界」に属するものであり、これについて納得して理解することは中学数学の最初の関門となるでしょう。また、そのようにして具体的な文脈から離脱した抽象的手法の適用によって、最終的に具体的な成果が得られたとしても、「狐につままれた」ような感じで納得しづらい、と思う人もいるのではないでしょうか。方程式を解いて「現実の世界」の答えが得られること、素数を平方和で表す方法の存在・非存在が複素数を使ってわかること(前回記事参照)、改めて考えてみると何だか魔法のようです。
筆者の場合、幸運にも中高数学の勉強の段階ではこのような抽象性について困難を感じずに済みましたが、大学レベル(現代数学)の勉強を始めた後は、多くの苦労を経験しました。現代数学ですと、一口に抽象化とは言っても最初から現実世界とは切り離された純粋数学の枠組内でのそれが多いので、その意味では「方程式の文章題」の例と様子が違っているのですが、それでも学習上の困難の在り方自体は上述したものと同様です。では、このような抽象性に由来する習得・納得の困難に立ち向かうためには、我々はどうすればよいのでしょうか?これは決まった答えのない難しい問題ですが、筆者なりに考えていることがいくつかあります。そこで次回は筆者の個人的な経験に基づいて、抽象的な数学の学習に関するいくつかのコメントを述べてみたいと思います。
**********
(意欲ある読者に向けた、答えのない演習問題)
1.様々な「方程式の文章題」について、「解法1」のような解き方と、「解法2」のような解き方を与え、それらを比較した考察を与えてみてください。
2.次回は、抽象的な数学を学ぶ上での困難にどのように立ち向かうか、ということを話題にしたいと思います。そのトイモデルとして、解法2に出てくるような方程式の同値変形の仕組みがわからず困っている人が、どのように学習を進めたら良さそうか、考えてみてください。(もちろん、どのような方法が最適かは人によると思いますが、その方法の候補を考えてみてください、ということです。)例えば、「解き方のパターンを、理屈は気にせず丸暗記する」という方法には、どのようなメリットとデメリットがあるでしょうか?また、こういった考察から、抽象的な数学の学習全般への示唆は何か得られるでしょうか?
━【「言語学をのぞいてみよう その40」(元K会英語科講師:野中大輔) 】━
2025年4月18日 更新
━【「言語学をのぞいてみよう その40」(元K会英語科講師:野中大輔) 】━
★このコラムでは、言語学を研究している筆者(元K会英語科講師)が、英語・言語学・外国語学習・比較文化などの話題をお伝えしていきます。★
たかが「カット野菜」、されど「カット野菜」
日本で最も有名な辞書と言えば『広辞苑』でしょう。2018年に『広辞苑』の第七版が出版された際は、10年ぶりの改訂ということで、各種メディアで取り上げられていました。特に注目が集まったのは新たに追加された項目で、「がっつり」や「婚活」などが収録されたことが話題になっていました。このように人の目を引きやすい項目がある一方で、特に話題にもならずひっそりと(?)追加されたものもあります。今回はそんな表現である「カット野菜」について考えてみます。
「カット野菜」なんて、わざわざ辞書に載せるほどの表現ではないように思った方もいるかもしれません。では、「カット野菜」とは何ですかと聞かれたら、うまく答えることができますか。そんなの、文字通り「カット」した「野菜」に決まっているじゃないか、と言いいたくなりそうなところですが、実は「カット野菜」の意味はそんなに単純ではありません。ここで『広辞苑』を見てみましょう。『広辞苑』は「カット野菜」の意味を(1)のように記述しています。
(1)そのまま調理でき、または食べられるように、適度な大きさに切って売られる野菜。
いかがでしょうか。意外と説明が長いと感じられた方がいるかと思います。(1)には「売られる」と書かれています。たしかに、カット野菜と言われて思い浮かぶのはお店で売られる商品です。自分で野菜を切った場合、それを「カット野菜」とは呼びませんね。そして、「そのまま調理でき、または食べられるように」の部分は、カット野菜が購入者の手間を減らすための商品であることを示す記述ですが、これはカット野菜の重要な特徴だと言えますね。
別の辞書も見てみましょう。(2)は『精選版 日本国語大辞典』における「カット野菜」の記述です。
(2)サラダとして食べたり、簡単に料理できるように、あらかじめ洗って切ってあるパック詰めの野菜。
こちらには「売られる」とは書かれていませんが、「パック詰め」となっていることから、結果的に商品であることがわかるような記述です。カット野菜はどれもビニール製の袋にパックされた状態で売られていますから、これも大事な情報です。また、「あらかじめ洗って」あるというのも、手間を省くための商品であることを伝える要素の1つですね。
「カット野菜」のように単純に思える表現でもその意味は意外と複雑であり、私たちはいつの間にかこのような複雑な知識を身につけて日々のやりとりを行っています。いつの間にか身につけている分、私たちはその複雑さに気づいていませんが、辞書は表現の意味をできる限り正確に記述しようと努めているわけです。辞書を見ることは、私たちが言語に関して身につけたものを考えるよいきっかけになります。特に、すでに知っているつもりの表現を引いてみるとおもしろいと思います。(1)と(2)のように、同じ表現でも辞書によって記述の仕方に違いがあるので、引き比べをするのもおすすめです(本記事では、『広辞苑』と『精選版 日本国語大辞典』を両方とも収録しているカシオの電子辞書Ex-word(XD-Z20000)を使用しました)。
英語講師のコラムのわりには、日本語の話を取り上げることが多いと思われるかもしれませんが、それは、普段から自分の母語を見つめ直し、言語について考える習慣をつくっておくことで、英語のような外国語を学習する場合にも気づけることが増えると思っているからです。たとえば英語のchopped cheeseという表現を聞いたときに、単にchop(切る、刻む)されたcheeseではないかもしれないから調べてみよう、と思えるようになります。外国語学習で大事なのは、そういったことの積み重ねではないでしょうか。なお、chopped cheeseが何なのか気になった方は、検索してみてください。
[おまけ]
「カット野菜」に近い英語の表現として、サラダ用のものだったらsalad kitがあります(kitは必要なものが一通りそろったセットを表す語)。たとえば、ドレッシングやクルトンが付いていて、袋を開けてすぐにシーザーサラダが作れるものはCaesar salad kitと呼ばれます。
★このコラムでは、言語学を研究している筆者(元K会英語科講師)が、英語・言語学・外国語学習・比較文化などの話題をお伝えしていきます。★
たかが「カット野菜」、されど「カット野菜」
日本で最も有名な辞書と言えば『広辞苑』でしょう。2018年に『広辞苑』の第七版が出版された際は、10年ぶりの改訂ということで、各種メディアで取り上げられていました。特に注目が集まったのは新たに追加された項目で、「がっつり」や「婚活」などが収録されたことが話題になっていました。このように人の目を引きやすい項目がある一方で、特に話題にもならずひっそりと(?)追加されたものもあります。今回はそんな表現である「カット野菜」について考えてみます。
「カット野菜」なんて、わざわざ辞書に載せるほどの表現ではないように思った方もいるかもしれません。では、「カット野菜」とは何ですかと聞かれたら、うまく答えることができますか。そんなの、文字通り「カット」した「野菜」に決まっているじゃないか、と言いいたくなりそうなところですが、実は「カット野菜」の意味はそんなに単純ではありません。ここで『広辞苑』を見てみましょう。『広辞苑』は「カット野菜」の意味を(1)のように記述しています。
(1)そのまま調理でき、または食べられるように、適度な大きさに切って売られる野菜。
いかがでしょうか。意外と説明が長いと感じられた方がいるかと思います。(1)には「売られる」と書かれています。たしかに、カット野菜と言われて思い浮かぶのはお店で売られる商品です。自分で野菜を切った場合、それを「カット野菜」とは呼びませんね。そして、「そのまま調理でき、または食べられるように」の部分は、カット野菜が購入者の手間を減らすための商品であることを示す記述ですが、これはカット野菜の重要な特徴だと言えますね。
別の辞書も見てみましょう。(2)は『精選版 日本国語大辞典』における「カット野菜」の記述です。
(2)サラダとして食べたり、簡単に料理できるように、あらかじめ洗って切ってあるパック詰めの野菜。
こちらには「売られる」とは書かれていませんが、「パック詰め」となっていることから、結果的に商品であることがわかるような記述です。カット野菜はどれもビニール製の袋にパックされた状態で売られていますから、これも大事な情報です。また、「あらかじめ洗って」あるというのも、手間を省くための商品であることを伝える要素の1つですね。
「カット野菜」のように単純に思える表現でもその意味は意外と複雑であり、私たちはいつの間にかこのような複雑な知識を身につけて日々のやりとりを行っています。いつの間にか身につけている分、私たちはその複雑さに気づいていませんが、辞書は表現の意味をできる限り正確に記述しようと努めているわけです。辞書を見ることは、私たちが言語に関して身につけたものを考えるよいきっかけになります。特に、すでに知っているつもりの表現を引いてみるとおもしろいと思います。(1)と(2)のように、同じ表現でも辞書によって記述の仕方に違いがあるので、引き比べをするのもおすすめです(本記事では、『広辞苑』と『精選版 日本国語大辞典』を両方とも収録しているカシオの電子辞書Ex-word(XD-Z20000)を使用しました)。
英語講師のコラムのわりには、日本語の話を取り上げることが多いと思われるかもしれませんが、それは、普段から自分の母語を見つめ直し、言語について考える習慣をつくっておくことで、英語のような外国語を学習する場合にも気づけることが増えると思っているからです。たとえば英語のchopped cheeseという表現を聞いたときに、単にchop(切る、刻む)されたcheeseではないかもしれないから調べてみよう、と思えるようになります。外国語学習で大事なのは、そういったことの積み重ねではないでしょうか。なお、chopped cheeseが何なのか気になった方は、検索してみてください。
[おまけ]
「カット野菜」に近い英語の表現として、サラダ用のものだったらsalad kitがあります(kitは必要なものが一通りそろったセットを表す語)。たとえば、ドレッシングやクルトンが付いていて、袋を開けてすぐにシーザーサラダが作れるものはCaesar salad kitと呼ばれます。
★春期セミナーのお知らせ★
2025年3月23日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
今回は春期セミナーのお知らせです!
数学者たちの研究、さまざまな分野とその世界
講演者:尾高悠志(京都大学大学院理学研究科准教授)
■日時 4月12日(土)15:00~17:00
■対象 新中学1年生~新高校3年生とその保護者
■料金 1,000円(当日受付にてお支払いください)
■会場 河合塾本郷校
勉強の延長に学者の仕事や研究があると言うのは確かなのですが、どのようにつながっていて、またどのように違うのでしょう。
そんなことをまったく知らない算数好きの少年だった私が30年弱前に中学受験をし、中学入学前に初めてK会に顔を出した時は非常に良いショックを受けました。学問としての数学の研究の道に突き進んでいく若くて活発な大学院生の講師陣に、本格的な数学の世界を垣間見せていただきました。それは、テストや成績を意識して頑張る勉強と、学問の研究の差に気がついて、私が学問としての数学にのめり込んでいく大きなきっかけとなりました。そのような経験を経て、今は数学者として数学三昧の生活をしています。研究と探究が毎日楽しくてたまりません。国際共同研究のためによく海外にも参ります。
本セミナーでは算数や数学が大好きな若いみなさんに、同じく算数や数学が好きで、かつそれを職業として選んだ私自身の経験や考えを、具体的な数学の話と織り交ぜながらお伝えしたいと思います。具体的な数学の話の中では、みなさんが途中で取り組める問題もご用意し、なるべくわかりやすいように努めます。また、個人的な話にはなりますが、整数や素数の話など(整数論・そして類体論)にK会ではまっていた私が今なぜ空間や図形の曲がり方に関わる研究をしているのか、できればそんな話もしたいと思います。
少年だった私にとってK会が数学者を志すきっかけの一つであったように、本セミナーが数学好きな若いみなさんの肥やしになれば、大変嬉しく思います。
≪講演者プロフィール≫
K会OB。筑波大学附属駒場高等学校卒。在学時に国際数学オリンピックに3度出場。2001年アメリカ大会金メダル、2002年イギリス大会銀メダル、2003年日本大会銀メダルを獲得。その後東京大学へ進学。同大理学部数学科を経て京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻を修了。2016年から京都大学大学院理学研究科准教授。2020年に日本数学会賞春季賞と学術振興会賞を受賞。
★お申込・各種お問合せ★
K会事務局:03-3813-4581
日・月を除く13:00~19:00の間でお電話を受け付けております。
★入塾・春期講習のお申し込みはWebから!★
お申し込みページへ
今回は春期セミナーのお知らせです!
数学者たちの研究、さまざまな分野とその世界
講演者:尾高悠志(京都大学大学院理学研究科准教授)
■日時 4月12日(土)15:00~17:00
■対象 新中学1年生~新高校3年生とその保護者
■料金 1,000円(当日受付にてお支払いください)
■会場 河合塾本郷校
勉強の延長に学者の仕事や研究があると言うのは確かなのですが、どのようにつながっていて、またどのように違うのでしょう。
そんなことをまったく知らない算数好きの少年だった私が30年弱前に中学受験をし、中学入学前に初めてK会に顔を出した時は非常に良いショックを受けました。学問としての数学の研究の道に突き進んでいく若くて活発な大学院生の講師陣に、本格的な数学の世界を垣間見せていただきました。それは、テストや成績を意識して頑張る勉強と、学問の研究の差に気がついて、私が学問としての数学にのめり込んでいく大きなきっかけとなりました。そのような経験を経て、今は数学者として数学三昧の生活をしています。研究と探究が毎日楽しくてたまりません。国際共同研究のためによく海外にも参ります。
本セミナーでは算数や数学が大好きな若いみなさんに、同じく算数や数学が好きで、かつそれを職業として選んだ私自身の経験や考えを、具体的な数学の話と織り交ぜながらお伝えしたいと思います。具体的な数学の話の中では、みなさんが途中で取り組める問題もご用意し、なるべくわかりやすいように努めます。また、個人的な話にはなりますが、整数や素数の話など(整数論・そして類体論)にK会ではまっていた私が今なぜ空間や図形の曲がり方に関わる研究をしているのか、できればそんな話もしたいと思います。
少年だった私にとってK会が数学者を志すきっかけの一つであったように、本セミナーが数学好きな若いみなさんの肥やしになれば、大変嬉しく思います。
≪講演者プロフィール≫
K会OB。筑波大学附属駒場高等学校卒。在学時に国際数学オリンピックに3度出場。2001年アメリカ大会金メダル、2002年イギリス大会銀メダル、2003年日本大会銀メダルを獲得。その後東京大学へ進学。同大理学部数学科を経て京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻を修了。2016年から京都大学大学院理学研究科准教授。2020年に日本数学会賞春季賞と学術振興会賞を受賞。
★お申込・各種お問合せ★
K会事務局:03-3813-4581
日・月を除く13:00~19:00の間でお電話を受け付けております。
★入塾・春期講習のお申し込みはWebから!★
お申し込みページへ
★情報科学(IS1)コースカリキュラム説明会のお知らせ★
2025年3月19日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
情報科学(IS1)コースのカリキュラム説明会のお知らせです。
■日時 3月23日(日)15:00~16:30
■対象 プログラミング初学者の中学2年生~高校3年生の方
初学者向けのコースなので、PC操作に不慣れな方も、コードを書くプログラミングの経験が無い方も気軽にご参加下さい!
説明会ではK会についてや情報科学のコースのご案内を簡単に行い、1時間ほどプログラミングに触れていただく予定です。
Java言語をベースにした初学者にも扱いやすいProcessingという環境で、図形を書いたり、動かしたりすることを通してプログラミングとはどういうものなのかを体験していただきます。
これはプログラミングのほんの入り口にすぎませんが、「楽しい!」「面白い!」と感じていただけたのならぜひ本格的な学習を始めましょう!
K会のカリキュラムは、全くの初心者から始めて約2年でアプリをつくったり、自分の実現したいプログラムを書けるようになるように組まれています。
また、情報科学の理論もしっかり扱うため、変化の激しい情報技術に振り回されるのではなく、それに対応し使いこなす力を養います。
※IS1コース詳細・シラバスはこちらを参照
≪入会までの流れのイメージ≫
3月23日(日)カリキュラム説明会
↓
4月2日(水)~4月5日(土)17:30~20:40 春期講習「Pythonではじめるプログラミング入門」
IS1コースの一時学期はPythonというプログラミング言語を中心に学習が進みます。
春期講習で一度この言語に触れておくことで、今後の学習がスムーズに進みます
↓
4月16日(水)または4月17日(木)1学期初回授業
説明会や、春期講習を経ても入会に不安が残る方はぜひ初回の授業にお越しください。
授業を体験することができます!
学校が終わってから塾に間に合うか、部活が重ならないかなど、新学期が始まってみないとわからないことも多いはずです。
そのような心配事があるみなさんは、焦らずに初回の体験を通してから入塾を判断しましょう。
ご相談ごとはK会スタッフがいつでも承ります!
★説明会のお申込・各種お問合せ★
K会事務局:03-3813-4581
日・月を除く13:00~19:00の間でお電話を受け付けております。
★入塾・春期講習のお申し込みはWebから!★
お申し込みページへ
情報科学(IS1)コースのカリキュラム説明会のお知らせです。
■日時 3月23日(日)15:00~16:30
■対象 プログラミング初学者の中学2年生~高校3年生の方
初学者向けのコースなので、PC操作に不慣れな方も、コードを書くプログラミングの経験が無い方も気軽にご参加下さい!
説明会ではK会についてや情報科学のコースのご案内を簡単に行い、1時間ほどプログラミングに触れていただく予定です。
Java言語をベースにした初学者にも扱いやすいProcessingという環境で、図形を書いたり、動かしたりすることを通してプログラミングとはどういうものなのかを体験していただきます。
これはプログラミングのほんの入り口にすぎませんが、「楽しい!」「面白い!」と感じていただけたのならぜひ本格的な学習を始めましょう!
K会のカリキュラムは、全くの初心者から始めて約2年でアプリをつくったり、自分の実現したいプログラムを書けるようになるように組まれています。
また、情報科学の理論もしっかり扱うため、変化の激しい情報技術に振り回されるのではなく、それに対応し使いこなす力を養います。
※IS1コース詳細・シラバスはこちらを参照
≪入会までの流れのイメージ≫
3月23日(日)カリキュラム説明会
↓
4月2日(水)~4月5日(土)17:30~20:40 春期講習「Pythonではじめるプログラミング入門」
IS1コースの一時学期はPythonというプログラミング言語を中心に学習が進みます。
春期講習で一度この言語に触れておくことで、今後の学習がスムーズに進みます
↓
4月16日(水)または4月17日(木)1学期初回授業
説明会や、春期講習を経ても入会に不安が残る方はぜひ初回の授業にお越しください。
授業を体験することができます!
学校が終わってから塾に間に合うか、部活が重ならないかなど、新学期が始まってみないとわからないことも多いはずです。
そのような心配事があるみなさんは、焦らずに初回の体験を通してから入塾を判断しましょう。
ご相談ごとはK会スタッフがいつでも承ります!
★説明会のお申込・各種お問合せ★
K会事務局:03-3813-4581
日・月を除く13:00~19:00の間でお電話を受け付けております。
★入塾・春期講習のお申し込みはWebから!★
お申し込みページへ
★物理コースカリキュラム説明会のお知らせ★
2025年3月14日 更新
みなさんこんにちは。K会事務局です!
物理(P1)コースのカリキュラム説明会のお知らせです。
■日時 3月23日(日)14:00~15:30
■対象 中学数学を一通り理解している中高生の方
このコースは微積分の計算ができることが前提となります。
ただし、春期講習「物理学入門」で必要になる数学の知識をレクチャ-するため、現時点では中学数学を一通り理解できていれば問題ありません。
説明会では、K会で学ぶ「物理学」が中高で学ぶ物理の内容とどう違うのかなどを講師よりご案内します。
学問として学ぶ物理の魅力や、面白さを知って頂けると嬉しいです。
※P1コース詳細・シラバスはこちらを参照
≪入会までの流れのイメージ≫
3月23日(日)カリキュラム説明会
↓
3月28日(金)~3月31日(月)17:30~20:40 春期講習「物理学入門」
微積分の計算に不安がある方は、入塾前にこちらの講習をご受講下さい。1学期の授業をよりスムーズにご受講いただけます。
日程が合わない場合は、春休みに教科書や参考書等で微積分の計算についてご自身で学習をしておきましょう。
↓
4月16日(水)1学期初回授業
説明会や、春期講習を経ても入会に不安が残る方はぜひ初回の授業にお越しください。
授業を体験することができます!
学校が終わってから塾に間に合うか、部活が重ならないかなど、新学期が始まってみないとわからないことも多いはずです。
そのような心配事があるみなさんは、焦らずに初回の体験を通してから入塾を判断しましょう。
ご相談ごとはK会スタッフがいつでも承ります!
★説明会のお申込・各種お問合せ★
K会事務局:03-3813-4581
日・月を除く13:00~19:00の間でお電話を受け付けております。
★入塾・春期講習のお申し込みはWebから!★
お申し込みページへ
物理(P1)コースのカリキュラム説明会のお知らせです。
■日時 3月23日(日)14:00~15:30
■対象 中学数学を一通り理解している中高生の方
このコースは微積分の計算ができることが前提となります。
ただし、春期講習「物理学入門」で必要になる数学の知識をレクチャ-するため、現時点では中学数学を一通り理解できていれば問題ありません。
説明会では、K会で学ぶ「物理学」が中高で学ぶ物理の内容とどう違うのかなどを講師よりご案内します。
学問として学ぶ物理の魅力や、面白さを知って頂けると嬉しいです。
※P1コース詳細・シラバスはこちらを参照
≪入会までの流れのイメージ≫
3月23日(日)カリキュラム説明会
↓
3月28日(金)~3月31日(月)17:30~20:40 春期講習「物理学入門」
微積分の計算に不安がある方は、入塾前にこちらの講習をご受講下さい。1学期の授業をよりスムーズにご受講いただけます。
日程が合わない場合は、春休みに教科書や参考書等で微積分の計算についてご自身で学習をしておきましょう。
↓
4月16日(水)1学期初回授業
説明会や、春期講習を経ても入会に不安が残る方はぜひ初回の授業にお越しください。
授業を体験することができます!
学校が終わってから塾に間に合うか、部活が重ならないかなど、新学期が始まってみないとわからないことも多いはずです。
そのような心配事があるみなさんは、焦らずに初回の体験を通してから入塾を判断しましょう。
ご相談ごとはK会スタッフがいつでも承ります!
★説明会のお申込・各種お問合せ★
K会事務局:03-3813-4581
日・月を除く13:00~19:00の間でお電話を受け付けております。
★入塾・春期講習のお申し込みはWebから!★
お申し込みページへ