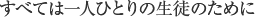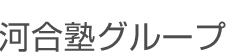サイエンス講座案内 講座案内・時間割 | K会 冬期講習
「なぜ、そうなるのか」をモットーに、楽しみながら科学する心を育みます。
【教科横断】LaTeX入門~数学書を作ろう~
受講目安
中高生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
LaTeXとは、主に数式を含む本や論文などを書くためのソフトウェアです。理工系の分野において世界中で数十年間、事実上の標準組版(文字・図版・写真などを配置する)ソフトとして用いられています。LaTeXはオープンソースのツールであり、WindowsやMac、Linuxでも無料で動くだけでなく、近年ではWebブラウザ上でも使えるようになったことから、多くの出版社や研究者、学生がさまざまな用途で活用しています。皆さんは学校の課題やレポートなどで数式や化学式を正しく、またはきれいに書きたいと思ったことはありませんか?本講座では、LaTeXをコンピュータにインストールするところから始めて、最終的にはレポートや論文はもちろん、プレゼンテーション資料(スライド)やポスターまで、学術的な文書を幅広くプロのように美しく作成できるようになることをめざします。文章の入力方法や、簡単な数式、表、画像の挿入などの基本的な操作から、マクロという自前の命令を作る方法までを手を動かしながら詳しく学んでいきましょう。有名なパッケージ(機能を拡張するためのもの)や、さまざまな応用例も紹介します。この4日間でぜひLaTeXの奥深さをじっくりと体験してみませんか。
テーマ
第1講 環境構築
第2講 文書作成
第3講 パッケージとマクロ
第4講 応用例
LaTeXを使うとこのようなことができます
画像の左側の画面に入力した内容が、右側の画面のように出力されます。
時間割・担当講師
- 日程
-
1月4日(日)~1月7日(水)
- 時間
-
10:00~13:10
- 講師名
-
宿田 彩斗
【情報】論理回路入門
受講目安
コンピュータの仕組みやプログラミングなど、情報技術に興味がある方を広く対象とします。電子工作の経験は問いません。
講座内容
近年研究が進む量子コンピュータは得意な問題が限られており、従来のコンピュータと置き換えられることなく共存していくと言われています。初期型からさまざまな進化を遂げ、現代ではパソコン・スマホ・ゲーム機といったかたちでだれもが手にするようになったコンピュータですが、その根幹を変わらず担っているのが「論理回路」です。論理回路とは、「0」と「1」の2種類の値を操ることで、複雑な処理を行う電子回路のことです。AND、OR、NOTといった、単純な計算操作の組み合わせで、四則演算やデータの記憶が実現でき、究極的には、現在のコンピュータの中枢であるCPUも作ることができます。本講座では、ICやLEDなどの電子部品をブレッドボード上でつなぎ、皆さんに実際に回路を組み立てていただきながら、論理回路の考え方や作り方を学びます。回路を組み立てる場面では、講師が一人ひとりをまわって丁寧に指導しますので、電子回路を作ったことがない方も大歓迎です。最後には、習得した内容を用いて自ら論理回路を設計し、組み立てて動かせるようになることが目標です。コンピュータの中で何が行われているのかを知ることは、プログラミングや他の情報技術を学ぶ際の確かな土台にもなります。机の上や手のひらの中、テレビの下で人知れず繰り広げられている「0」と「1」の世界について、一緒に学んでみませんか。
テーマ
第1講 論理回路の初歩
第2講 論理式と真理値表
第3講 2進法と加算器
第4講 記憶回路
このような道具を使います①
基板
人間でたとえるならば、心臓の役割を果たします。スマートフォンや、ゲーム機などみなさんが普段使っている電子機器にはこうした基板が埋め込まれています。
このような道具を使います②
ブレッドボード
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられるため、電子工作が初めての方でも簡単に扱えます。
時間割・担当講師
- 日程
-
12月25日(木)~12月28日(日)
- 時間
-
14:00~17:10
- 講師名
-
森 裕淳
【情報】人工知能入門~ゲームAIを作ろう~
受講目安
プログラミングの経験がある方(if文、for文などがわかる方)を対象とします。
講座内容
IBMのワトソンがクイズ番組で優勝したり、コンピュータ将棋がプロ棋士に勝利したりするなど、人工知能は目覚しい発展を遂げてきました。ここ数年では、画像生成AIやChat GPTの発表を皮切りに数々の生成AIサービスが発表され、人工知能は私たちにとってさらに身近な存在となりつつあります。また、膨大な量のデータの山から有益な情報を引き出す方法(アルゴリズム)も年々進歩しており、入力されたデータが何なのか、何に属するのかを判断する「認識」、入力されたデータから未来に起こることや隠れていて見えない部分の情報を考える「予測」、入力に基づき適切な行動を選択する「意思決定」などを行うためのさまざまなアルゴリズムも提案されています。本講座では、まずProcessingという言語の復習を行います。次に人工知能がどのような考え方で動いているのかを学び、その後、「強いオセロの対戦相手」や「弾を避けるように動く敵キャラ」、「行動を学習して反撃するボス」などがどのようにすれば作れるのかを考え、実装していきます。言語はProcessingやPythonなどを使う予定です。皆さんの積極的な参加をお待ちしています。
テーマ
第1講 Processing の復習
第2講 AI のアルゴリズム
第3講 AI を作ってみよう(1)
第4講 AI を作ってみよう(2)
時間割・担当講師
- 日程
-
12月20日(土)~12月23日(火)
- 時間
-
14:00~17:10
- 講師名
-
瀬戸 友暁
【物理】量子コンピュータ入門~物理と情報の融合~
受講目安
指数・対数の計算ができることを前提とします。
講座内容
ネット・ショッピングやキャッシュレス決済など、私たちの暮らしを支える暗号技術の世界は転換期を迎えています。これまで用いられてきたRSA暗号と呼ばれる素因数分解の困難性を利用した暗号、つまり桁数の多い合成数をコンピュータが素因数分解できない(膨大な時間が必要になる)ことを根拠に安全とされてきたものが、実は量子力学を用いたアルゴリズムで現実的な時間内に解読可能であると判明したのです。このアルゴリズムの鍵は、従来のコンピュータで用いられている0か1かのビットではなく、「0と1の重ね合わせ」を実現できる「量子ビット」にあります。量子ビットを用いて作る「量子コンピュータ」は、実用化をめざし、大学・企業を問わず世界中で研究が進められています。量子ビットを用いた演算は、直感的にはわかりにくいかもしれません。しかし、基礎的な部分であれば高校までの数学、及び行列の知識で十分に理解が可能です。本講座では、量子コンピュータについて、その理論的基礎である量子力学の導入から始め、量子ビット、演算回路について扱った後、実際に素因数分解を行うアルゴリズムであるショアのアルゴリズムを理解することをめざします。時代の最先端を行く量子コンピュータの世界の一端を、本講座で学んでいきましょう。
テーマ
第1講 量子力学の基礎
第2講 量子ゲートと量子テレポーテーション
第3講 量子フーリエ変換と位相推定
第4講 ショアのアルゴリズム
時間割・担当講師
- 日程
-
12月20日(土)~12月23日(火)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講師名
-
粟野 稜也
【化学】美しい鉱物の色の世界 ~軌道論でひもとく化合物の色と発光~
受講目安
中高生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
皆さんは世界が色に満ちあふれている理由を考えたことはありますか?そもそも、“色”とは何なのでしょう。たとえば、「鉛筆は黒い」「海は青い」「スマートフォンの画面はさまざまな色を表示できる」といったことにも本来は理由があります。この原理を化学は鮮やかに解き明かしてくれます。しかし、高校で習う化学では多くの場合いろいろな現象を暗記することにとどまります。たとえば有機化学の反応、無機化合物の色や沈殿、「ボーアモデル」や「電子殻」といった存在も暗記した、もしくはこれから暗記する方が多いはずです。理論的に説明できるはずなのに、暗記に頼るのはなぜでしょうか?それは、「軌道」という難しい概念が必要になるからです。そこで本講座では、化学に必要不可欠でありながら高校教育では十分に扱われることがない「軌道」を、4日間かけてじっくり理解することをめざします。この講義を通じて、限られた人のみぞ知る奥深い化学の世界を味わってみませんか。軌道の概念を会得し、鉱物や染料などの美しい色の謎を解明する楽しさをぜひ体感してください。なお、本講座では「軌道」のみならず、大学物理(量子論)の基礎を同時に会得することができます。物理学に興味がある方にとっても有意義な内容となっています。
テーマ
第1講 化学と数学の❝いろは❞
第2講 フロンティア軌道論と錯体
第3講 化合物の色と発光
第4講 結晶構造と鉱物の色
時間割・担当講師
- 日程
-
1月4日(日)~1月7日(水)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講師名
-
吉田 悠真
【生物】免疫学入門~生物学オリンピックと医師国家試験を題材として~
受講目安
中高生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
地球上で最も多く人間の命を奪っている生物は、蚊です。とは言っても、ライオンやワニなどのように物理的に襲ってくるのではなく、寄生虫やウイルスなどの「病原体」を運んでくることによって、マラリアやデング熱などの感染症に罹患してしまうのです。マラリアは結核やHIV/AIDSと並んで「世界三大感染症」として恐れられており、マラリア治療薬のアルテミシニンを発見した屠呦呦氏には、抗寄生虫薬のイベルメクチンを発見したウィリアム・C・キャンベル氏と大村智氏とともに、2015年ノーベル生理学医学賞が授与されています。本講座では、このような寄生虫・ウイルス・細菌に代表される病原体について、実践的な問題演習をもとに概観していきます。また、このような病原体に対して、人間が実際にどのような防御機構(免疫)を有しているのか、あるいはワクチンや血清療法などの治療法を開発しているのかを、生物学オリンピックや医師国家試験などの演習を通して、可能な限り現代的な理解をめざしていきます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを経験した私たち人類は、これまでどのように感染症と闘ってきて、これからどのように生きていくのか、この微生物学と免疫学の2日間で模索してみませんか。
テーマ
第1講 病原体と感染
第2講 自然免疫と適応免疫
このような問題を考えます
時間割・担当講師
- 日程
-
12月27日(土)・12月28日(日)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講師名
-
熊谷 勇輝
【地理】フィールドワークの手法と実践
- 過年度とは問題が異なるため、再受講が可能です。
受講目安
中高生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
地理の授業では、自然や社会の中で起こっているさまざまな現象について学びます。教科書や図録を開けば、多種多様な地形や町の様子が写真や絵などを用いて描写されているでしょう。では、これらの知識はどのように蓄えられていったのでしょうか。先人たちは実際に現地を訪問し、そこで何が見られ、何が起こっているのかを記録することで知識としていきました。このような試みを「フィールドワーク」と言います。地形や気候などを扱うフィールドワークにおいては、自然の中でさまざまな観察・観測を行うことが必須です。これにおいては、特殊な器具からメモ帳まで、種々の道具を用いて記録を行なっていきます。講座の前半では、この自然地理のフィールドワークの手法や実践について解説します。また、都市や社会などを扱うフィールドワークについては、街中で観察を行い記録をつける必要があります。このようなフィールドワークでは、自然地理のそれとは異なり複雑な器具を用いる機会は多くありません。しかしながら、目で見たものを記録することは、思いのほか難しく、困難なことがあるのです。講座の後半では、この人文地理のフィールドワークの手法や実践について解説します。
テーマ
第1 講 自然地理のフィールドワークの手法
第2 講 自然地理のフィールドワークの実践
第3 講 人文地理のフィールドワークの手法
第4 講 人文地理のフィールドワークの実践
時間割・講師担当
- 日程
-
12月15日(月)~12月18日(木)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講師名
-
中尾 俊介
【天文学】予選直前!天文学オリンピック問題演習会
受講目安
指数・対数の知識があることを前提とします。
講座内容
天文学オリンピックとは、2022年に第1回が開催された天文学の知識・思考力・技能を競う大会で、予選・本選の二段階の試験を経て、受賞者が決定されます。本講座では、毎年冬に行われる天文学オリンピックに向けて、過去の問題を題材に演習と解説を行います。第1・2講では予選問題を扱います。予選は選択式で問題数が多く、限られた時間で効率よく解答する力が求められます。特に天文学では、単位変換や法則の使いこなし等の天文学特有の計算に慣れることが解答速度を高める鍵となります。続く第3・4講では本選問題を取り上げます。本選は理論試験と実技試験に分かれ、未知の現象を題材にしたり、一貫したテーマで構成されたりする問題も多く、解き進める中で大きな学びを得られるのが特徴です。第3講では系外惑星観測に関する問題を扱い、第4講では本選の中でも特にデータ解析の要素が強い問題に取り組みます。実際に手を動かしながら、本選で求められる実践的な経験を積んでいきましょう。問題演習を通じて、単なる解法練習にとどまらず、天文学の奥深さや新しい発見の喜びを皆さんと共有できることを楽しみにしています。なお、本講座は関数電卓を使用します。お持ちの方はご持参ください。
テーマ
第1 講 予選 天文学特有の計算①
第2 講 予選 天文学特有の計算②
第3 講 本選 系外惑星観測
第4 講 本選 天体の運動
このような問題を考えます①
このような問題を考えます②
時間割・担当講師
- 日程
-
1月4日(日)~1月7日(水)
- 時間
-
10:00~13:10
- 講師名
-
早川 晴
【言語学】言語学オリンピックで入門する言語学 ~基本編~
- 過年度とは問題が異なるため、 再受講が可能です。
受講目安
中高生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
みなさんは「言語学オリンピック」をご存知でしょうか。「いくつ言語を話せればいいの?」「どうやって順位づけするの?」と思われる方も多いでしょう。国際言語学オリンピック委員会は「言語学や言語に関する知識は必要なく、最も難しい問題であっても論理的思考力や忍耐強い努力、常識に囚われない発想力があれば解ける」と述べています。日本委員会でも「問題は実際の言語研究で行われる分析に似ていて、『初めて見る言語のデータから隠れた法則を解き明かす』というものです。謎解きやパズルのように、分析力、情報処理能力、論理的思考、試行錯誤する力が求められます。」としています。しかし、言語学オリンピックに立ち向かう際には、実際の問題を解いて慣れていくだけではなく、特にフィールドワークで未知の言語の文法書を記述する「記述言語学」や、世界の言語に見られる普遍的な法則を記述する「言語類型論」の知識を得ることも必要です。本講座によって、言語学オリンピックでの問題解決能力が向上するだけでなく、学校で教えられる日本語や英語の伝統的な文法が相対的に捉えられるようになり、国語や英語に関する語学上の理解もよりいっそう深まるでしょう。
テーマ
第1講 ルールと遊び方
第2講 音声学・音韻論
第3講 形態統語論・言語類型論
第4講 文字論・命数法
★JOLでは、たとえばこんな問題に挑戦します
国際言語学オリンピック(IOL)とは…
日本言語学オリンピック(JOL)とは…
時間割・担当講師
- 日程
-
12月25日(木)~12月28日(日)
- 時間
-
14:00~17:10
- 講師名
-
小林 剛士
言語学オリンピックで入門する言語学~演習編~
- 過年度とは問題が異なるため、再受講が可能です。
受講目安
中高生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
理論物理学者J・J・サクライは “The reader who has read the book but cannot do the exercises has learned nothing.”「本を読んだが練習問題ができないという読者は何も学んでいないのだ」という格言を残していますが、これは理論物理学に限らず記述言語学やその能力を競う言語学オリンピックにも当てはまります。ただ書籍を読むだけでも、演習問題をこなすだけでも実力はつきません。能力を高めるためには、演習を積み重ねながら、その背後にある構造や理論をつかみ、深い理解に達することが必要です。また、こうした学習は言語学を学び始めたばかりの初学者には難しく、優れた先導者が欠かせません。本講座では、言語学オリンピックの国際大会(IOL)・アジア太平洋大会(APLO)・日本大会(JOL)の良問を題材に、講師と生徒のディスカッションによる質の高い演習を積んでいきます。本講座を通して、言語記述に対する高い実力と言語理論に対する深い理解をめざしましょう。
テーマ
第1講 音韻論
第2講 形態論
第3講 統語論
第4講 文字論・命数法
時間割・担当講師
- 日程
-
12月25日(木)~12月28日(日)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講師名
-
岡本 沙紀
-
資料請求はこちら