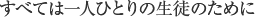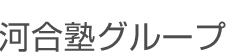各講座詳細-探究的な学びを深める- みらい探究プログラム K-SHIP | 体験授業・イベント
探究的な学びを深める
問いを立て、情報を集めて考察し、答えを創り出す力を養います。主体的な学びの力が身につくプログラムです。
私たちの生活を支える“発明”は、特別な人だけのものではありません。
本講座では「発明とは何か?」という素朴な疑問から始め、知的財産や特許制度の基礎をわかりやすく解説します。また、日本の発明データや特許情報検索データベースを実際に操作しながら、先人たちのアイデアに触れ、自分の発想を形にするプロセスを体験します。
身近な“困りごと”からアイデアを生み出すワークや「発明のウソ・ホントクイズ」で創造力を刺激し、理系・文系に関係なく、普段の生活から「新しい視点で世界を見る力」を育みましょう!
講師プロフィール
吉田 拓也(東大寺学園中学校・高等学校 情報科教諭)
修士(学術)
日本情報科教育学会 情報科教育連携委員
日本知財学会 知財教育分科会 副代表
日本産業技術教育学会 学会賞(2022年度奨励賞・2023年度優秀実践事例賞)
日本教育情報化振興会 ICT夢コンテスト優良賞(2022・2023年度)
内容
「発明とは何か」を入口に、知的財産の基礎やアイデアの広げ方をやさしく学ぶ。
(1)「発明」ってなんだ?をひもとく
発明の仕組みや特許・知的財産について理解する
実例を通して「発明は誰のものか」を考えつつ、アイデアを形にする流れを知る
(2)みんなの中の「発明力」を引き出す
クイズやワークで、身近な“困りごと”からアイデアを生み出す練習を行う
日本や世界の発明のデータにも目を向け、発想を広げる方法を体験する
発明は特別な人だけのものではない!だれでも始められる発明・創造の第一歩を学ぶ講座です。
■ご受講にあたって
・Zoomを使用します。タブレットやスマートフォン、パソコンでご参加ください。パソコンをお持ちの場合はパソコンでの利用を推奨します。
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
論文にはルールがあります。それは皆さんが「総合的な探究の時間」に作成する論文やレポートから、ノーベル賞級の発見が記された本格論文に至るまで共通するものです。
本講座では、実際の論文や例題を用いて、論文の「読み方」「書き方」を学習します。論文のルールを知れば、正確かつ効率的に論文が読めるようになり、客観的で説得力のある文章を書けるようになります。文献の探し方も伝授しますので、皆さんが探究テーマを探す際にも役立ちます。本講座で「巨人の肩の上に立つ」学問の世界への扉を開けましょう。
*「読む編」は2025年6月~8月・11月~12月、「書く編」は2025年11月~12月に実施した講座と同じ内容です。
講師プロフィール
加賀 健司(河合塾講師)
河合塾では、小論文や生物、情報の授業を中心に活躍。医系小論文や資格講座でも「文章の論理的な捉え方」「何をどのように表現すればよいか、伝わりやすいまとめ方」など、わかりやすく授業を展開する、文章のスペシャリスト。
内容
-読む編-
「論文を読む」動画視聴・ワーク時間:約90分
・論文って何だろう
・文章の基本・パラグラフとその構成
・序論/本論/結論
・論文を探そう
-書く編-
「論文を書く」動画視聴・ワーク時間:約90分
・本論を書く
・結論を書く
・序論を書く
・論文を引用しよう
*本講座は、皆さんのご都合にあわせて、動画を視聴してワークに取り組むオンデマンド型講座です。視聴期間中は、何度でも繰り返し視聴することができます。
*課題の提出・添削などはありません。
■ご受講にあたって
・送信予定日の前日までにお申し込み(お支払い)が完了した方へ、お申し込みいただいたメールアドレス宛に視聴方法とID・パスワードをお送りします。
送信予定日:3/4(水)、3/11(水)、3/18(水)、3/25(水)
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
この講座に関するよくあるご質問
Q.小論文講座と何が違いますか?
A.小論文は出題者がテーマを設定し、参考文献を用意し、限られた字数の中で書くことが求められていますが、論文は自分でテーマを設定し、自分で参考文献を探し、字数をかけて論じるものです。本講座では、論文のルールを理解して、論文を正しく読めることを目標にしています。
Q.入試に役立ちますか?
A.はい。総合型選抜などの入試では、近年、小論文をはじめレポートを課す大学が増えています。一般入試だけでなく、そのような入試にも対応が可能です。
受講生の声
・今まで論文を読むのにも自分で論文を書くのにも苦手意識を持っていましたが、少し頑張ってみようと思えました。
・確認テストによって講座全体の理解度を深めることができ、自分がこれから書く論文やレポートに生かしていきたいと思えた。
・自分で都合のつく時に受講できるのがいいと思った。また、ワークがあることで受け身だけの講座にならなくてよかった。
・論文を読むから書くへと、段階的に分けて講座を行っていたので、「論文はここが重要で引用の仕方はこんな感じ」などが分かりやすかった。
・論文のどの部分に何を書けばよいか、わかるようになった。課題研究の授業があるので、そこでの論文を、この講座を生かして書けるようにしたい。
・先生の話はわかりやすかったし、面白かった。また機会があったらやりたい。
 過去のラインアップ
過去のラインアップ
ご受講にあたって
-
みらい探究プログラム