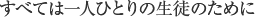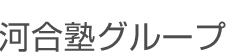高槻中学校・高等学校 鈴木 優子先生 教員・受検者の声 | ケンブリッジ英語検定|河合塾ケンブリッジ英語検定事務局
ケンブリッジ大学出版による世界標準の英語教育で、英語を使って生徒から正解のない答えを引き出す授業を実践
高槻中学校・高等学校
英語科主任
鈴木優子先生
ケンブリッジのチューターがつき、一緒に検証しながら授業をレベルアップ
――御校でケンブリッジ英語を導入した経緯を教えてください。
鈴木先生:本校の校長の決定事項として「受験英語からの脱却」と宣言して、2020年からケンブリッジ大学出版局(以下、ケンブリッジ)が世界に向けて提供する英語教育プログラム「ケンブリッジ英語」を導入しました。導入にあたっては、ケンブリッジの厳しい審査を受け、Better Learning Partner の認定を日本で初めて受けました。
――Better Learning Partnerに認定されると、どんな教育プログラムを提供されるのですか?
鈴木先生:ケンブリッジ英語は、英語教育の考え方、教材、教育メソッドなどトータルな英語教育のプログラムです。Better Learning Partnerに認定されると、英国本国の担当者や、ケンブリッジが認定する国際的な英語指導資格をもつネイティブの先生が私たち教員のチューターとなり、一緒にカリキュラムや授業を作り上げていきます。本校は中高一貫校なので、まず中1から導入し、学年進行でケンブリッジ英語を学ぶ教員も、生徒も増やしていきました。初年度は、本校の教員としては、中1を担当していた私ともう1人の教員2人が取り組みました。
具体的には、年度が始まる前の3月に、ケンブリッジのテキストを使ってどうやって教えるのか、どんな目標をもって4技能で育てていくのかという研修を2日間みっちり行いました。4月からは最低月に1回はチューターと一緒にオンラインで授業の検証を行いました。夏にはワークショップを行い、秋にはチューターが来校して、授業を見学し、フィードバックを行いました。
3学期には授業のビデオや教員・生徒に対するアンケートをもとに英国の担当者からインタビューを受けて、振り返りを行いました。これを毎年繰り返して、授業を向上させていきます。今年で導入6年目を迎え、導入時の学年は高3になりました。
なお、高3はケンブリッジ英語ではなく、日本の大学受験に対応し対応した、入試問題の演習を行っています。
授業はその日焦点を当てることだけに注力 教師は生徒のファシリテーターに
――ケンブリッジ英語を取り入れたときの状況を教えてください。
鈴木先生:まずテキスト見て、これはとても難しいと感じました。中1のテキストなのに単語レベルが高く、日本語が全くありません。リーディングのテキストの最初は掲示板に貼ったクラブ活動の紹介でした。内容は楽しいのですが、三単現のsも命令文も知らない生徒にAll Englishでどうやって教えればいいかわかりませんでした。そこでチューターに、内容を全て理解させるのは無理だと言うと、「Why?」としか言わないんですね。「なぜ、全てわからせる必要があるの?この単元は、掲示板から何らかのクラブの情報を得るのが目的でしょう?」
と言うんですね。しかし私には抵抗があり、出てきた文法事項を教えたりしていました。
文法も、日本の教科書と全く違う順番で出てくるので、それにも抵抗しました。文法事項を全て網羅することは難しく、これはもしかしたら、間違っているのかもしれないと気付くのに、そう時間はかかりませんでした。
――先生の考えは、どうように変わっていったのですか?
葛藤しながら、それでも4技能を使わせる授業を行っていると、テキストの中に出てくる文法も難しく感じていた表現も形を変えて何度も出てくることに気づきました。
だから1回の授業では、ポイントだけ教えればいいということです。教えすぎないことの大切さに気づき始めたのはこのころです。チューターがいつもStudent Centered と言っていた意味が解り始めたということですね。
例えば、ある日の中学2年生の授業では、「自分のアバターを作る」というものがあり、生徒達は「とがった髪はどう表現するの?」「ロボット見たいな手は?」など、難しい形容詞を自分たちで表現するために調べていました。アウトプットを行うために、自らの力で学ぶ力が養われていると思いました。
ケンブリッジのテキストは、英語を母語としない人に対する英語教育法を練りに練って作り上げたものだと思います。細かいことは問いません。他方、細かいことを気にしすぎるのが、日本人が英語を話せない最たる理由ではないでしょうか。文法の間違いを気にすると話せなくなってしまいます。そうではなく、どんどん話してどんどん書くことで、「使える」英語が身につくことがわかりました。
特に中学生のときは「楽しい」ということを一番意識するようにしました。チューターからは、教師の役割はファシリテーターで、教えるのではなく英語で質問して子どもたちから答えを引き出すことだと言われました。ケンブリッジのテキストには必ず答えのない問いがあり、それに対する答えを生徒達が導きだす瞬間が最も生徒達がキラキラする瞬間です。生徒達の可能性は無限であり、私たちはそれに蓋をしてはいけないのだと思いました。そのことに気づき始めた時、劇的に私の授業の視点も変わり、生徒達の姿勢も変わり始めました。
――文法などの誤りは、どこで直すのですか?
鈴木先生:スピーキングのときに誤りを指摘すると話そうという気持ちがしぼんでしまうので、誤りはライティングの授業で直します。でも、その日のテーマが三単現のsだったら、単数形や複数形が間違っていたとしても、そこはあまり強調しすぎないようにしました。それは、必ず別の場面でそのことに取り組むことができるからですね。
また、定期考査の英作文の問題では、減点はせずに加点します。とにかく恐れずたくさん話そう、書こうというのがケンブリッジ英語の考え方です。
ケンブリッジ英語・ケンブリッジ英語検定で大学入学共通テスト、自由英作文が得意に
――導入したときの保護者の方の反応はいかがでしたか?
鈴木先生:保護者に納得していただくのは、時間がかかりました。
自分たちが経験してきた英語の学び方のほうが安心されるのだと思います。私も、時には校長も、保護者会などで丁寧に説明し、コロナ禍スタートの学年で、オンライン授業を実施していたので、保護者の方が生徒の近くで授業に参加されていましたね。
導入当初は、外部の模試や学力テストで結果が出ず焦ったこともありましたが、諦めず、日々の授業を行い続けていると、中2の途中から結果が出るようになりました。
現在、英語の特別なバックグラウンドなしで本校に入学した生徒も驚くような英語力を身に付け、英検準1級以上の合格者もこれまでにない数をだしてくれています。海外研修で現地の方々とそん色なくコミュニケーションを行い、プレゼンを行う姿を見ることができたことはとても誇らしいことでした。保護者の方々も安心してくださっていると感じています。
――ケンブリッジ英語検定はいつから導入し、いつ受検していますか? また、試験対策はしていますか?
鈴木先生:ケンブリッジ英語検定は、ケンブリッジ英語が目指す英語力を評価する試験です。ですので、試行の意味もあり、ケンブリッジ英語導入前年の2019年に採用したのが始まりです。本校では現在、中2でA2、高1でB1を全員が受検しています。ケンブリッジ英語のテキストそのままなので、スピーキング試験の形式や注意事項を伝えたり、高1が受検するB1のリスニングはイギリス英語なので何回か練習したりする程度で、特別な試験対策はしていません。
――ケンブリッジ英語とケンブリッジ英語検定を導入することによる、大学入学共通テストや二次試験への影響はありそうですか?
鈴木先生:ケンブリッジ英語導入後初の大学受験は来春ですが、本校では、高1から毎年その年の共通テストを解かせています。高1は問題全体で平均7割強、高2ではリスニングは8割、リーディング8割弱程度点数がとれています。二次試験の自由英作文も得意ですね。反面、和訳や英訳は、英語を英語で理解しているのになぜ日本語で理解する必要があるの?と抵抗感があるようです。ただ入試には必要なので、現在高3では、そこを重点的に勉強しています。文法の4択問題も苦手ですが、出題が減少しつつありますので、良かったと思っています。
English Educational Partnerに認定され、英語の教育から英語を使った教育へ
――日本全体の英語教育について、課題だと感じることはありますか?
鈴木先生:人によるとは思いますが、一番問題なのは、先生が間違えたり、評価されたりするのを気にしすぎることです。先生も人間、間違えるのは当たり前であり、それを隠す必要もないし、それを見せることで生徒達も、間違えることは恐れることではないというマインドになっていきます。間違えたら、そこから学べばいい。そういったことを繰りかえすことで、教室は安心・安全な場所になっていきます。英語は言葉であり、人とコミュニケーションをとるためのツールです。失敗したら怖いというマインドでは人とコミュニケーションをとることはできませんね。安心・安全な場所だからそれができるようになります。コミュニケーションのツールだということにフォーカスすれば、無駄なものが見えてくる。日本の教育が変わっていくためには、英語だけではなく、全ての点について考える必要があるかと思いますが、大学受験に合格するためだけの英語は子供達の可能性に蓋をしているように思えます。
――御校の英語教育の、今後の抱負について教えてください。
鈴木先生: 今年度、ケンブリッジとEnglish Educational Partner(※2)という、Better Learning Partnerより上位のパートナーシップ契約を結びました。English Educational Partnerに認定されたのは、日本ではまだ本校だけです。私は中1だった生徒が高3になるまで一通り経験して、ケンブリッジの目標や考え方をほかの先生に伝えていく役目をいただきました。ケンブリッジ英語の授業を初めて担当する先生や、ある程度経験のある先生に対するケンブリッジからの支援はこれまで同様です。
今後は、ケンブリッジと連携しながら、英語を使って子どもたちを教育するという1つ上の目標に向かっていきます。ケンブリッジのテキストを使って生徒たちがどう考え、発想して発信するかをもっと大切にしていくのだとは思いますが、具体的にどうすればいいかは、模索中です。ケンブリッジの方とも議論しながら、本校の生徒に合った英語の授業にしていきたいと、楽しみにしているところです。
-----------------
(※1)Better Learning Partnerとは
ケンブリッジの総合的なコンサルティング(独自のカリキュラム作成~教員研修まで)のもと、教員の指導力向上を中心として、学校全体の英語力を向上させる3年計画に取り組む学校。現在は、English Educational Partnerに統合されています。
(※2)English Educational Partnerとは
Cambridgeとのパートナーシップにより優れた英語教育を達成するためのコミットメントの証です。
-----------------
2025年8月インタビュー実施
お問い合わせ
- お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせの対応のみに利用します。
- 受付時間外にお問い合わせを頂いた場合は翌営業日以降のご回答となります。ご了承ください。