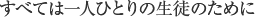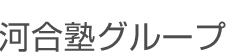各講座詳細-教科の学びを深める- みらい探究プログラム K-SHIP | 体験授業・イベント
教科の本質をとらえる
教科の「見方・考え方」を学ぶことで、本質に迫ります。「おもしろかった」の1歩先へ行くプログラムです。
 教科「情報」で学ぶ、重要分野を押さえよう
教科「情報」で学ぶ、重要分野を押さえよう
若者の読解力が落ちている-これは、昔からよくある言説かもしれませんが、大学入試の現代文対策を長年指導してきた河合塾だからこそ、近年、そうした状況を切実に感じています。読解に必要な基礎知識や考え方を身につけていない、あるいは間違った考え方を身につけているため、短期間の受験勉強では、入試現代文が求める読解力まで届かない生徒さんもいるのです。
ここでは、本格的な受験勉強にとりかかる前のお子様をもつ保護者の方とともに、読解力が低下している状況を河合塾視点から共有して、その背景を考えていきたいと思います。
講師プロフィール
梅澤 眞由起(河合塾講師)
河合塾の模擬試験・教材作成を担当し、入試問題の本質を知り尽くしている講師。読む力を確実に伸ばすだけでなく、文章を読むことが好きになる授業を展開します。
内容
・河合塾の立場から、文章を論理的に読んで解くことの難しさを提示します
・読解で間違える生徒の実態をお見せして、その理由と、ではどうすればよいかを考えていきましょう
■ご受講にあたって
・Zoomを使用します。タブレットやスマートフォン、パソコンでご参加ください。パソコンをお持ちの場合はパソコンでの利用を推奨します。
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
昨年秋に好評を博した「もう泣かない数学」の第二弾。
今回のテーマは「三角比から三角関数へ」。未習の方もぜひご参加ください。
数学の勉強を頑張っているけれど、結果に結びつかずに、悩んでいる方は多いのではないでしょうか?それは、頑張る方向を間違えているのかもしれません。本講座では、日常の身近な題材を用いて「数学の考え方」「数学の正しい頑張り方」を紹介します。「問題が解けない」=「数学ができない」ではありません。この講座で数学の見方・考え方を身につけて、数学で「もう泣かない」自分を手に入れましょう。
講師プロフィール
下町 壽男
元県立高校校長
数楽共育コンシェルジュ
Japan International School(タシュケント&サマルカンド)エグゼクティブアドバイザー
内容
・数学が苦手な人向き
・問題を解くことを目的にしません
・数学で学ぶ内容が、日常生活につながることを知る
・単位円を使いこなすことで、三角関数の理解を深めます
■ご受講にあたって
・Zoomを使用します。タブレットやスマートフォン、パソコンでご参加ください。パソコンをお持ちの場合はパソコンでの利用を推奨します。
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
受講生の声
(第一弾「もう泣かない数学 -数学の見方・考え方・学び方-」より)
・数学に苦手意識を強く感じていたのですが、そうではなくもっと簡単に捉えるところから数学の勉強というものを始めればいいのだと感じました。
・公式を丸暗記するのではなくなぜそうなるのかの過程や基礎の大切さを再認識することができた。
・数学に対する苦手意識を少しでも改善することができとても助かりました。
・今、数学を頑張っている最中なので改めて楽しんでやろうと思いました。
・もう泣かないようにしたい。
現代社会ではさまざまなメッセージが発信されています。それをきちんと読み解けなければ、生きていくうえで不自由が生じ自分の力を発揮することが難しくなります。
では、社会で役立つ読解力はどのようにして得られるのでしょうか。実は、入試現代文で必要となる読解力は社会で役立つ読解力に繋がっています。
本講座では、読解力の根幹をなす「論理的に考える力」の大切さを学びます。数多の生徒を悩ませた問題文と設問を通じて「論理的であるとはどういうことか」を学び、世の中に氾濫する怪しげな文章・表現を観察することで「論理的でないとはどういうことか」についても学びます。
この講座で「本物の読解力」「社会で役立つ読解力」向上への第一歩を踏み出しましょう!
講師プロフィール
益満 重虎(河合塾講師)
河合塾で長きにわたり模擬試験「東大入試オープン」作成の中心的メンバーをつとめ、授業でも読解の本質をとらえる講義で、多くの受験生を志望校合格へ導く。
内容
・論理的に読まないことで間違いがちな問題と設問を提示します
・論理と自分の主観・思い込みを区別することの大切さを知ります
・世の中に存在する怪しげなメッセージを論理的に読むことで、「論理的ではない」とはどういうことかを学びます
■ご受講にあたって
・Zoomを使用します。タブレットやスマートフォン、パソコンでご参加ください。パソコンをお持ちの場合はパソコンでの利用を推奨します。
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
心理実験、やってみませんか?
今回の講座では、参加者のみなさん自身が実験参加者となり、実際に「記憶に関する実験」に挑戦します。シンプルな実験ですが、その結果を集めてグラフにしてみると、人間の記憶には意外な規則性が隠されていることがわかります。実験を通して、脳の仕組みを少しだけ研究者の気分でのぞいてみましょう。
また、データ解析には表計算ソフトを使います。難しい操作ではありませんが、コンピュータや統計を活用する現代の心理学の姿を体験できるはずです。
受講後には、普段の勉強法や暗記の工夫につながるヒントも“おまけ”として見えてくるかもしれません。
*「高校で学ぶ心理学」のご受講が初めての方でもお申し込みいただけます。
*「表計算ソフト」の環境が整っていない場合でも、一部は手作業で集計できる内容となっていますので、ご安心ください。
講師プロフィール
武善 紀之(日出学園中学校・高等学校情報科 公民科教諭)
認定心理士
高等学校情報科用教科書 「新編情報Ⅰ」「情報Ⅰ Step Forward!」「情報Ⅱ」編集委員(東京書籍、2022年~)
NHK高校講座「情報Ⅰ」監修講師(2023年~)
内容
1.講座の概要
心理学の歴史とともに、さまざまな学問との繋がりを知る
「心」を学ぶ上で、人間の「認知の仕組み」を知る
人工知能・認知心理学
2.記憶実験をやってみよう
「人の心」をコンピュータになぞらえて、統計的に解き明かそう
3.記憶に関するさまざまな知見を知る
*パソコンからご参加ください。
*スプレッドシートを利用した操作を行います。Googleアカウントをお持ちでない方は、アカウントを取得いただくことを推奨いたします。
■ご受講にあたって
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
受講生の声
(2025年実施「高校で学ぶ心理学 -わたしたちの思い込みと情報のトリック-」より)
・情報はあまり心理学に関係ないと思っていたが、心理学と情報は非常に近く、かつ、日常生活にも大きく関わっていることが興味深く、楽しかった。
・講座を受ける前に考えていた心理学と認知心理学がかなりかけ離れていて面白かったです。
・身の回りで起こる錯覚や、使いやすい使いにくいの違い、データの正誤、因果関係など身近な具体例を用いて説明してくださり、分かりやすかった。
・心理学に統計学が関わっているのは知っていたが、思ったよりも情報学、ないしは人体工学と深い関わりを持っていて、文理の横断的分野なのだと改めて強く感じた。
・自分は倫理を勉強していて、共通テストでも使いたいと考えているので、心理学の部分ももう一度復習してみようと思います!
・講座内容が面白くてあっという間の時間でした。ありがとうございました。
「最近、英文がうまく読めなくなってきた。単語はやっているし、文法も一通り終えたし、模試も受けている。なのにどうして?」
このような悩みは誰もが抱えているものです。志望校のレベルが高ければ、英文が読めないという症状を「致命傷」のように感じたり、英語の文章がだんだん怖く見えてきたりします。
そもそも「英文が読める」というのはどういうことなのでしょう? ハイレベルな英文が正確に読める人の頭の中では何が起きているのでしょう?「英語力の正体」って何なのでしょう?これが明らかになれば「なぜ自分は英文がうまく読めないのか」が見えてきます。そして、同時に「具体的に何をすれば英文がうまく読めるようになるか」が見えてきます。
残念ながら特効薬があるわけではありません。しかし「英語力の正体」を見極めたうえで自分の弱点を強化する努力を続けていけば、確実に最短距離で「英文が読める」という状態に到達することができます。本講座は、ハイレベルな英文読解力へと向かう道のりの確かなスタート地点となることでしょう。
講師プロフィール
佐藤 進二(河合塾講師)
河合塾および河合塾マナビスで医学部コースから早慶対策講座まで幅広く授業を担当。『Asahi Weekly』(朝日新聞社)では「英訳・天声人語で英文読解」の連載中。近著に『英文法語法QUAD』(Z会、共著)がある。
内容
・なぜ大学入試で「英文読解」が課されるのか
・求められる「2種類の英語力」
・言語習得のプロセス
・「英文が読める」とはどういうことか
・音と読解の関係
・入試で何が問われているのか―入試問題演習
・読解力向上のために何をすればいいのか
■ご受講にあたって
・Zoomを使用します。タブレットやスマートフォン、パソコンでご参加ください。パソコンをお持ちの場合はパソコンでの利用を推奨します。
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
 教科「情報」シリーズ
教科「情報」シリーズ
現代社会に不可欠な「情報活用能力」を身につけるためのシリーズ講座です。教科「情報」の重要単元だけでなく、学問や将来のキャリアにもつながる講座もラインアップ。1講座からご受講いただけますが、シリーズを通して受講することで「情報」の世界を体系的に学ぶことができます。
デジタルデータに囲まれた世界でいきる私たち。
気がついたらスマートフォンやタブレットの容量がない!と困ったことはないですか?
ファイルの種類がたくさんあるけど実は違いがよくわかっていない…なんてことはないですか?
本講座では、そんな日頃のあるあるを題材に「情報Ⅰ」でも重要な領域のひとつであるデジタル表現とは何かを整理し、データ圧縮の重要性やその仕組みを学びます。また、簡単な画像を圧縮する実習を通して、さまざまな技術と場面に応じた有効な使い方を体験します。
これがわかればタイパ良し!コスパ良し!
データをコンパクトにして世界を飛び回ろう!
講師プロフィール
蓮池 隆(早稲田大学 創造理工学部 経営システム工学科教授)
早稲田大学理工学術院 創造理工学部経営システム工学科、計画数理学研究室教授。数理最適化を利用した意思決定支援システムの開発、意思決定支援のための感情・感性に対する客観的数理モデリングなどを研究。日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本経営工学会、システム制御情報学会等に所属、IEEEメンバー。
内容
・デジタル表現とは何か
・データの圧縮がなぜ必要なのか?
・簡単な画像を使って、圧縮技術を体感する
・身近な圧縮技術でできること。その仕組みを理解する
・さまざまな事例から、場面に合わせた適切な方法を知る
■ご受講にあたって
・Zoomを使用します。タブレットやスマートフォン、パソコンでご参加ください。パソコンをお持ちの場合はパソコンでの利用を推奨します。
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
理系・文系問わず全国の中高生に、プログラミングを身近に感じてもらいたい!
本講座では、エラーが起こらないやさしい環境で、楽しみながら“本物のプログラミング”に近い体験をします。さらに、ただ操作するだけではなく「なぜ高校生が今プログラミングを学ぶのか」「コンピュータはどんなことを得意としているのか」といった視点についてもしっかり学びます。
scratchよりも少し本格的な仕組みのブロック型言語を使い、Pythonが初めての人でも安心してプログラミングの基礎に触れることができる講座です。
プログラミングの世界へ「最初の一歩」を踏み出してみませんか?
講師プロフィール
遠山 紗矢香(静岡大学 情報学部 准教授)
工業高校情報技術科を卒業したのち、大学院情報学研究科にて博士(認知科学)を取得。
小学生から大学生までの情報教育において、認知科学に基づく実践研究を行う情報教育のエキスパート。
情報処理学会理事(教育担当)、文部科学省学校DX戦略アドバイザー等を務めている。
内容
1.プログラミングはなぜ大事なのか
2.学校の勉強とプログラミングの関係性
3.プログラミングを体験する
4.プログラミングの強みを活かす
*初学者、プログラミングが苦手な方を対象とした講座です。
*プログラミングを学んでいない方も受講できます。
*実際にプログラムを書く講座ではありません。
*EduBlocksを利用し、テキストベースの言語でコーディングする方法を扱います。
*パソコンからご参加ください。
■ご受講にあたって
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
本講座では、皆さんがよく知っているゲームのキャラクターデータを使用して、実習を行いながらデータサイエンスにおける各種分析方法の理解を深めます。
データを処理・分析し、評価する学問であるデータサイエンスは、私たちの周囲にある物事から新しい価値を創造するものです。現在の情報社会には欠かせないものというだけでなく、「数学Ⅰ」「情報Ⅰ」といった高校での学習や共通テストとも密接につながっています。
本講座を通して、未来に役立つ「データを分析し、活用する力」を身につけましょう。
*2025年3月23日に実施した講座と同じ内容です。
講師プロフィール
蓮池 隆(早稲田大学 創造理工学部 経営システム工学科教授)
早稲田大学理工学術院 創造理工学部経営システム工学科、計画数理学研究室教授。数理最適化を利用した意思決定支援システムの開発、意思決定支援のための感情・感性に対する客観的数理モデリングなどを研究。日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本経営工学会、システム制御情報学会等に所属、IEEEメンバー。
内容
・問題の発見からデータの収集・整理、分析・可視化、結果の検証・評価まで、データサイエンスの流れをつかむ
・与えられたデータから基本的な特徴をつかむ(基本統計量の確認、散布図・ヒストグラムなどを描く)
・見える特徴や予想した相関の検証を行う(単回帰分析・重回帰分析など)
・さまざまな分析手法を用いて、データの特徴をみる(主成分分析・クラスタリングなど)
・得られた結果より、新しいデータの分類を行うなど、さまざまなデータから、正しい見方・考え方・結果のとらえ方を学ぶ
*パソコンからご参加ください。
*「数学Ⅰ」と「情報Ⅰ」を履修済みであることを前提とした内容です。
*Google Colaboratoryを利用して、実際にデータの分析操作を行います。Googleアカウントをお持ちでない方は、新たにアカウントを取得してください。
■ご受講にあたって
・講座実施4日前から順次お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomのID・パスコードをご案内します。
・データ通信費は受講者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
この講座に関するよくあるご質問
Q.「情報」や「数学Ⅰ」を履修していなくても受講できますか。
A.受講は可能です。ただし、「情報Ⅰ」「数学Ⅰ」で学習するデータ分析に関する用語(※)は知っておいてください。専門的な分析手法などは、できる限りわかりやすく説明しながら進めますので「情報Ⅱ」は履修前でも問題ありません。
※データ分析に関わる用語:ヒストグラム、散布図、相関係数、回帰直線、中央値、四分位数 など
Q.受講対象の学年ではありませんが、受講することはできますか。
A.「数学Ⅰ」や「情報Ⅰ」で学んだことを活用する内容ですので、「数学Ⅰデータの分析」「情報Ⅰデータの活用」の内容を学習済みであれば受講は可能です。
Q.プログラミングの経験がありませんが、大丈夫でしょうか。
A.プログラムの作成経験はなくても大丈夫です。先生の指示(ソースコード)に従ってGoogle Colaboratoryを動かすことができれば、問題ありません。
Q.文系で、数学は苦手ですが、受講することはできますか。
A.受講可能です。本講座で扱う内容は文理を問いません。ご興味のある方はどなたでもご参加いただけます。
Q.スマートフォンやタブレットで受講できますか?
A.Google Colaboratoryを利用するため、パソコンでの受講をお願いします。
Q.学校のGoogleアカウントは使えますか。
A.設定により、Google Colaboratoryが使えないことがあります。その場合は、新たにGoogleアカウントを取得してください。
受講生の声
・データサイエンスは広い分野で利用されているので、その重要性を改めて感じました。分析の切り口を工夫することによって、データの見え方が変わることを実感できました。
・データサイエンスを学ぶために理系を志そうとした時期がありましたが、別にこれからは文理問わず、社会の必須能力となるということを知った。
・データ分析により、新しい宝を発見出来ると思った。
・この講座を通じてデータサイエンスは思った以上にいろいろな分野で活用されていることを知りました。今回学習したことを活かして、色々なデータ分析に挑戦してみたいです。
・データサイエンスの面白さを知ることができました。また、瞬時にデータを分析できるプログラミングの便利さを実感しました。これから情報やプログラミングの勉強を頑張ろうと思います。
本講座ではネットワークの基礎知識からしくみの理解と、さまざまな暗号化技術の理解を深めます。
「情報Ⅰ」や「情報Ⅱ」で扱う情報通信ネットワークや情報システムについて、苦手意識のある方、今使っているスマートフォンや自宅のネットワークのしくみが知りたい方など大歓迎!
私たちの生活に欠かせないインターネットの世界・ネットワーク通信は、世界中の誰もが通信内容を見ることができるガラス張りの世界です。そんなガラス張りの世界で、私たちの大切な情報を相手に正しく・安全に伝えるためには、どうすればよいでしょうか?
情報の安全なやり取りのしくみを正しく楽しく理解しましょう!
内容
・情報のやりとりのしくみを学び、コンピュータを正しく理解する
・プライバシーとセキュリティ
・暗号通信の実験、暗号の世界を体感する
受講生の声
・普段の生活や、試験においても役立つ内容で、とても楽しかったです。
・理解していないにも関わらず日常的に目にするので何の疑念も持たずにネットを利用していましたが、先生の説明を聞き、以前より少し安心して利用できると思います。
・今までデジタルの暗号化など表示され目にはしていたが何かわからずそのままにしていながらも気になっていました。今回とても深いものだと知ることができて興味深かったです。
・インターネットのしくみについて色々な工夫や技術がつかわれていることがすごいと思った。
・とてもわかりやすく勉強になりました。暗号を実践できたのも楽しかったです。ありがとうございました。
「ゾウを見たことがない人に、ゾウがどんな生き物であるかを説明してください」
この問いには情報デザインの本質の一端が含まれています。共通テストでも出題される領域でありながら、何を学ぶのかイメージがつかみにくい「情報デザイン」。実は皆さんの日常生活にも深く関わるだけでなく、論理的思考力、コミュニケーション能力、問題解決能力を高めるためにも大変重要な内容です。
本講座では、身近な事例をもとに、演習を通して情報デザインの要素である「表現」「機能」「論理」について学びながら、日常にも入試にも役立つ視点を楽しく身につけることができます。「情報デザイン」と聞いて感じるモヤモヤが「なるほど!」に変わる瞬間をぜひ体験してみましょう。
教科「情報Ⅰ」の試作問題では、文化祭の模擬店の待ち状況を考える問題が出題されました。また、本試験では、おつりを渡すために用意すべき千円札の枚数に関するシミュレーションをテーマとする問題でした。いずれも、似たような一連の分析を体験し、確率モデルのシミュレーションの考え方を理解しておくことがポイントとなります。
シミュレーションといえば、気候変動予測など複雑なもの、難しそうなものをイメージしますが、実は共通テストでも出題されたように、みなさんにとっても日常的に行っていることもあるのです。今回は、身近な事例からシミュレーションを使って物事を考える手法を学びます。
世の中には膨大なデータが存在し、私たちの生活はそれらをさまざまな形で活用することで成り立っています。
本講座では、まずデータの種類や扱い方といった基礎を学び、グラフによる可視化ややさしい統計手法を体験します。さらに、身近な事例を取り上げながら「相関」と「因果」の違いを考え、データをどのように読み解けばよいかを探っていきます。また、講義の中で実際に、参加者の皆さんがデータを収集・分析する活動も体験することで、学んだ知識を実践へとつなげていきます。
こうした学びを通して、データを正しく理解し活用するための基礎知識、数字やグラフを批判的に読み解く力、そして情報に基づいて考え判断する主体的な姿勢を養うことができます。
内容
(1)データ収集、分析、可視化の基本を学ぶ
・データの構造化、質的データ、量的データとは何か
・適切なグラフを選択できる?
(2)実生活での活用方法を体験し、データの重要性を実感する
・本当にその因果関係は正しい?
受講生の声
・なんのためにデータを使うのかそのデータはどのような原因と結果から起きているのかを考える考え方を知ることができた。
・分かりやすいスライドと具体例とともに説明してくださったので、情報が不得意の私でも、理解できました。
・めちゃくちゃ楽しかったです。自分の意見を言えるのもいいし、相手の意見とも比較ができて新しい発見がありました。
・ちょうど習ったばっかりの内容で復習にもなったし、分からなかったところがこの講座で理解することができた。
・中学生でも納得できそうなくらいわかりやすかったです!
広くみんなに知ってほしい! 文系・理系の垣根を越えて、基礎からはじめるデータサイエンス。
データを処理・分析し、評価する学問であるデータサイエンスは、私たちの周囲にある物ごとから新しい価値を創造します。現在の情報社会には欠かせないものというだけでなく、「数学Ⅰ」「情報Ⅰ」といった高校での学習や共通テストと密接につながっています。
本講座では、人気ランキングやアンケートなど身近な事例を用いて、データの読み解き方、グラフの表現の仕方を学びます。情報社会を歩く地図をここで手に入れましょう。
内容
・問題の発見からデータの収集・整理、分析・可視化、結果の検証・評価まで、データサイエンスの流れをつかむ
・目的に合わせたデータの集め方
・正しく伝わるデータの見せ方
・データから、正しい見方・考え方・結果のとらえ方を学ぶ
受講生の声
・ハードルが高い学問というイメージだったが、身近なことや日々の発想の中に、データサイエンスを活かす機会はたくさんあると思った。
・グラフを見た時に、見た瞬間の直感だけで考えると本質からずれていることがあることに改めて気づけた。また、このような力は将来において役立つと思った。
・情報Ⅰや数学で学ぶデータの分析、そういった学問に対する具体的なイメージがなかなか持てず、正解も分かりづらく、困っていたのですが、今日の講座のおかげで、面白さを感じ始めるきっかけになった。
・データサイエンスは難しいイメージがあったけれど、確率や統計の例をいくつも示してくれて、楽しく理解することができた。今後の高校の授業に前向きな気持ちになった。
・データサイエンスにおけるものの考え方を学ぶことができ、共通テストの「情報」でもその考え方を活かせそうだと思った。
 過去のラインアップ
過去のラインアップ
ご受講にあたって
-
みらい探究プログラム