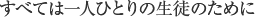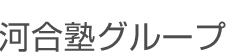医進生応援プログラム 特別講座「未来の医師たちへ」 イベントレポート | 体験授業・イベント
医師という仕事を理解し、医師へのモチベーションを高める濃密なひととき
2018年6月24日(日)に河合塾麹町校(全国医進情報センター)にて、中学生・高校生とその保護者の方を対象に、医進生応援プログラムの第1弾として、「未来の医師たちへ」と題する特別講座を開催しました。第1部では、東京医科歯科大学再生医療研究センター教授の岡本隆一先生をお招きして特別講演会を実施。第2部では、河合塾出身の現役医学生たちを迎えてトークライブを行いました。そして第3部では、河合塾の進学アドバイザーが、2018年度医学部入試を振り返りつつ最新の入試情報を伝えました。
- 日時
-
2018年6月24日(日)13:00~17:00
- 会場
-
河合塾 麹町校
- 対象
-
中学生・高校生と保護者の方
第1部 特別講演「医学の未来と再生医療」
岡本先生からは、医師には病院で診療を行うだけでなく多様な進路があること、そのキャリアの積み上げ方、未来の医療と再生医療に関するお話をいただきました。
最初に、医学部を卒業し、医師免許を取得した後のキャリアの多様性について紹介されました。先生ご自身も、診療のほかに、医学の研究や医学生の教育に携わっておられますし、他にも医学教育の専門家や、公衆衛生の専門家、さらには企業に就職したり起業したりして研究成果を世の中に広める人など、多くの道があるとのことでした。このなかで東京医科歯科大学の教育にも触れられ、1年次から病院実習があることや、研究に没頭する期間があること、研究者養成コースがあることなどの特長をご紹介いただきました。
次に、医療の変化の速さについてお話しいただきました。電子カルテを例にあげながら、先生が医師になった頃と現在では、病院が大きく様変わりしていることを具体的に説明され、未来の医療については、AIの進歩などにより、診療結果や身体の情報は身体に装着した機器からの自動入力になり、電子カルテさえも無くなるのではないかと予想されました。やがては臓器もプリンターでつくる技術が可能になるのではないかというお話に、会場の参加者は驚いたような顔をして聞き入っていました。
続いて、先生のご専門である再生医療の話題に移りました。iPS細胞のようにどんな臓器にもなれる能力はないものの、特定の臓器ならどの細胞にもなれる体性幹細胞についてわかりやすく説明してくださり、先生ご自身は、腸上皮の体性幹細胞を使って、難病である炎症性腸疾患を直す治療法を研究していることを、画像や映像などを駆使して具体的に紹介いただきました。
最後に、会場にいる未来の医師に向けて、「考え続けることを大事にしてほしい」「患者の声に真摯に耳を傾けてほしい」「心と身体を律してほしい」と、エールを送られました。
第2部 河合塾卒業生・現役医大生によるトークライブ
慶應義塾大学1年生、東京慈恵会医科大学2年生、東京医科歯科大学3・4年生、千葉大学5年生の現役医学生5人が参加しました。
医師をめざしたきっかけから、現在の1日の生活の様子、興味を持って学んでいる授業、将来の夢など、いろいろと語ってもらいました。学年も大学も異なる方に集まってもらったため、さまざまな医学部の多様な学びについての本音を知ることができました。基礎医学の勉強の大変さ、感染症の原因となる虫の話、研究活動の面白さ、臨床実習でのリアルな経験など、医学生の生活が生き生きと浮かびあがり、受験生やその保護者はときに真剣な眼差しで、ときに笑顔になりながら、聞き入っていました。
医学部受験のことに話題が向けられると、とにかく最後まで諦めないで頑張ることが大切だと、意見が一致しました。悩んだり困ったりしたらとにかく誰かに相談すること、文系科目は論理的思考を鍛えるためにあること、学科試験では1位になれなくても医師になりたい気持ちは1位だと自分を励ます気持ちが大切なことなど、経験に基づいたアドバイスは受験生にとって大きな励ましになったことでしょう。
第3部 進学アドバイザーによる入試情報講演
河合塾の進学アドバイザーが、2018年度の医学部入試を振り返り、医学部受験に向けた心構えなどを伝えました。
最初に、近年の医学部入試の動向について、具体的な志願者数の変化などをあげながら、2015年以降は人気上昇に歯止めがかかっている実情に触れつつ、模試などの状況から、来年度の医学部志願者もやや減少するだろうとの見通しを示しました。
ただし、国公立大の場合は、河合塾調べではセンター試験の合格者平均得点率は87%、二次試験の合格者平均偏差値67.4であること、私立大でも合格者平均偏差値が65.5であることを指摘し、決して易化したわけではないことを強調しました。特に国公立大では、苦手科目があると合格が困難であることを詳しいデータ分析によって紹介しました。
また、近年は推薦入試の割合が高まっており、医学部へのもう一つのルートとして前向きに考えてほしいこと、医学部入試で重要な面接試験では、「相手の立場に立って気持ちを理解する、話を聞く」というコミュニケーション能力が重要であることを力説し、特にコミュニケーション能力については「普段から心がけてください」と奮起を促しました。